登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品販売を担う専門資格です。
2009年の薬事法改正により誕生しましたが、薬剤師が不在の場合でも、第2類・第3類医薬品の販売などを通じて、地域住民のセルフメディケーションを支える重要な役割を担っています。
この記事では、その仕事内容、薬剤師との違い、給与、多様な就職先、そして誰でも挑戦可能な資格取得方法までを網羅的にわかりやすく解説します。セルフメディケーション推進の要として注目される登録販売者の魅力と現状への理解を深めましょう。
\あなたに合った職場をお探しします!/
登録販売者とは?

登録販売者とは、2009年の薬事法改正(現:医薬品医療機器等法)により誕生した、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売を担う専門資格です。
薬剤師が不在の場合でも、第2類・第3類医薬品の販売や情報提供を通じて、地域住民のセルフメディケーションを支える重要な役割を担います。この改正は、薬剤師不足や国民の医薬品アクセスの向上、セルフメディケーション推進の必要性を背景に、新たな医薬品販売体制として導入されました。
この記事では、登録販売者について以下の点を詳しく解説します。
● 2009年の薬事法改正で誕生した背景
● 薬剤師との違い
● 具体的な仕事内容と活躍の場
● 給料・年収事情
● 資格取得方法と試験の概要
● 将来性とキャリアパス
登録販売者資格は、簡単に言うと医薬品専門の販売士です。
出典:厚生労働省|薬事法の一部を改正する法律等の施行等について
医薬品販売のスペシャリストとしての位置づけ
登録販売者は、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品(OTC医薬品)の販売をする専門家です。
役割は単に商品を販売するだけでなく、購入される方一人ひとりの症状や状態を聞いて、適切な医薬品を選び出すための情報提供や相談対応をすることです。
一般用医薬品は、医師の処方箋なしで購入できる反面、誤った使用は健康被害につながるリスクも伴います。
登録販売者は、第2類医薬品や第3類医薬品に関する専門知識を活かし、効能効果、副作用、正しい使い方、他の薬との飲み合わせなどをていねいに説明します。購入される方が安全かつ効果的に医薬品を使用できるようにサポートするのです。
特に、薬剤師が不在でも、登録販売者がいると消費者には安心して医薬品を購入できる体制が確保されていることになります。これは、地域住民の健康維持・増進や、軽度な疾病の初期対応(セルフメディケーション)を推進する上で非常に重要な位置づけと言えるでしょう。
購入される方の疑問や不安を解消し、時には医療機関への受診を勧めるなど、医薬品販売の最前線で安全を守る専門家としての責任を担っています。
出典:
厚生労働省医薬・生活衛生局長|登録販売者に対する研修の実施について
日本登録販売者会|登録販売者の倫理規程と業務マニュアル
2009年の薬事法改正で誕生した背景
登録販売者制度は、2006年に改正され、2009年までに全面施行された薬事法(現:医薬品医療機器等法)によって誕生しました。
それ以前の一般用医薬品販売は、薬剤師が全ての医薬品を扱える「一般販売業」のほか、都道府県知事の試験による「薬種商」が指定医薬品以外の一般用医薬品を販売できる「薬種商販売業」など、許可業態ごとに販売可能な品目が規定されていました。
しかし、国民のセルフメディケーション推進のため、医薬品のリスクの程度に応じた専門家の適切な関与と情報提供が求められるようになりました。
そこで、薬剤師などが薬局や店舗に常に配置される体制の代わりとなる、より実効性のある仕組みとして登録販売者制度が導入されたのです。
この改正により、一般用医薬品はリスクに応じて第1類から第3類までに分類され、それぞれの情報提供のあり方が重点化されました。そして、薬剤師または登録販売者が薬局や新たな許可業態である「店舗販売業」などで、このリスク分類に基づく医薬品販売と情報提供を担う体制が整備されました。
登録販売者は、都道府県知事が行う試験により資質が確認される専門家として位置づけられ、医薬品販売制度において重要な役割を担うことになったのです。
出典:厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課|医薬品販売制度の変遷
薬剤師との違いは何?
薬剤師と登録販売者はどちらも医薬品に関わる専門家ですが、その資格の位置づけ、業務範囲、取り扱える医薬品の種類に明確な違いがあります。
まず、資格について、薬剤師は大学の薬学部(6年制)を卒業し薬剤師国家試験に合格する必要がある国家資格です。一方、登録販売者は学歴や実務経験を問わず、各都道府県が実施する試験に合格し、登録を受けることで資格を得られます。
最も大きな違いは、取り扱える医薬品の範囲と調剤業務の可否です。
【薬剤師と登録販売者の違い】
| 薬剤師 | 登録販売者 | |
| 資格 | 6年制薬学部卒業後、国家試験合格 | 学歴・実務経験は問わない、都道府県知事による登録販売者試験合格 |
| 調剤の可否 | 可 | 否 |
| 取り扱える医薬品 | 医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、第3類) | 一般用医薬品(第2類、第3類) |
要指導医薬品とは、医療用医薬品から市販薬に変わったばかりの薬などのことです。慎重に販売する必要があるため、販売の際、薬剤師が購入される方の情報を聞くとともに、対面で書面に医薬品に関する説明をすることが義務付けられています。
薬剤師はすべての医薬品の取り扱いと調剤が可能ですが、登録販売者は第2類・第3類医薬品の販売と情報提供に特化した専門家と位置づけられています。
登録販売者の仕事内容と役割

登録販売者の主な仕事は、一般用医薬品の販売と、購入される方への適切な情報提供です。具体的には以下の業務を担います。
● 情報提供: 医薬品の効能効果、副作用、使用上の注意などを説明
● 商品管理: 在庫管理、発注、品出し、売り場作り
● その他店舗業務: レジ対応、清掃など
法律(医薬品医療機器等法)により、登録販売者には医薬品の適正使用を確保するための情報提供(第2類医薬品は努力義務、第3類医薬品は規定なし)や、購入される方からの相談に応じる義務が定められています。
副作用が疑われる場合は、厚生労働省への報告も重要な責務の一つです。単に商品を売るだけでなく、購入される方を含めた住民の健康を守る専門家としての役割が求められます。
出典:
厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課|医薬品販売制度の変遷、日本登録販売者会|登録販売者の倫理規程と業務マニュアル
一般用医薬品(第2類・第3類)の販売と説明
登録販売者が主に扱うのは、一般用医薬品の中でも第2類医薬品と第3類医薬品です。これらの医薬品を販売する際には、適切な情報提供が不可欠です。
第2類医薬品は、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むため、購入される方から相談がなくても、効能効果、副作用、使用上の注意点などについて情報提供に努める「努力義務」があります。
「指定第2類医薬品」は、小児や妊婦などが使用する場合に特に注意が必要なため、より積極的な情報提供が求められ、専門家による対応が義務付けられています。情報提供は、購入される方の状況を伺いながら、添付文書の内容に基づき口頭で行うのが基本です。
第3類医薬品は、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含みます。法律上、情報提供は義務付けられていませんが、購入される方から相談があった場合には、適切に応じる義務があります。
実際の接客シーンについて、風邪薬を購入したい人への情報提供例を以下に示しました。
【登録販売者の情報提供内容の例】
| 接客シーン | 情報提供内容 |
| 症状のヒアリング | 「いつからどのような症状がありますか?(例:喉の痛み、鼻水、熱など)」「他に何かお薬は飲んでいますか?」「アレルギーはありますか?」 |
| 商品提案と説明 | (症状に合わせ商品をいくつか提示し)「こちらのお薬は、〇〇という成分が喉の痛みを和らげ、△△という成分が鼻水を抑える効果があります。眠気が出ることがありますので、服用後の運転はお控えください。1日3回、食後に服用してください。5~6回服用しても症状が良くならない場合は、医療機関を受診してください。」 |
| 疑問点の確認 | 「何かご不明な点はございますか?」 |
一方的な説明ではなく、購入される方とのコミュニケーションを通じて必要な情報を的確に伝えることが重要です。
出典:
厚生労働省|指定第2類医薬品について、厚生労働省|一般用医薬品のリスク区分について
お客様の症状に合わせた商品提案
登録販売者に求められる重要なスキルの一つが、購入される方の訴えをていねいに聞き取り、最も適した一般用医薬品を提案することです。このプロセスでは、以下の点に注意が必要です。
まず、症状のヒアリングを的確に行います。
「いつからですか?」
「具体的な部位はどこですか?」
「他に服用中の薬はありますか?」
「アレルギー体質ですか?」
「妊娠中・授乳中ですか?」
「これまでに薬で副作用が出たことはありますか?」
.
といった質問を通じて、使用者の状態を把握するのです。
次に、ヒアリング内容と医薬品の専門知識を基に商品を提案します。その際、なぜその医薬品が適しているのか(成分、効能効果)、他の選択肢と比較してどのような特徴があるのかを分かりやすく説明します。
ただ使用を勧めるだけでなく、あくまで一時的な症状緩和が目的であることを伝え、一定期間使用しても改善しない場合や、症状が悪化する場合には医療機関を受診するよう促す「受診勧奨」も重要です。
受診勧奨の具体的な判断基準としては、症状が重篤である、長期間続いている、原因が特定できない、一般用医薬品での対応が困難と思われる場合などがあげられます。医薬品選択の根拠は、添付文書情報や薬学的な知識に基づき、使用者の年齢、体力、生活習慣なども考慮して総合的に判断します。
登録販売者に求められるのは、安全性を最優先し、少しでも不明な点やリスクを感じた場合は、薬剤師に相談したり、受診を強く勧めたりする慎重さです。
\あなたに合った職場をお探しします!/
登録販売者になるための資格と条件

登録販売者になるには、各都道府県が年に1回実施する「登録販売者試験」に合格する必要があります。この試験の大きな特徴は、受験資格に学歴や実務経験などの制限が一切ないことです。
主なポイントは以下の通りです。
● 受験資格:年齢、学歴、実務経験、国籍などに関わらず誰でも受験可能。
● 難易度:近年の合格率は全国平均で40~50%程度で推移。しっかりとした対策が必要。
試験合格後、実際に登録販売者として働くためには、勤務先の都道府県で「販売従事登録」を行う必要があります。この登録を経て、初めて登録販売者として一般用医薬品の販売などに従事できます。
出典:
厚生労働省|令和6年度登録販売者試験実施状況、厚生労働省|令和5年度登録販売者試験実施状況、東京都保健医療局|登録販売者販売従事登録について
受験資格は誰でもOK?
登録販売者試験の最大の魅力の一つは、受験資格に一切の制約がない点です。「実務経験〇年以上」や「薬学部卒業」といった条件は全く必要ありません。年齢、学歴、職歴、さらには国籍も問われず、医薬品の専門家を目指したいという意欲があれば、誰でも挑戦できます。
門戸の広さから、実際に多様な方々が登録販売者として活躍しています。例えば、東京都医薬品登録販売者協会が2022年に行ったアンケート調査(有効回答319名)では、現役の登録販売者の性別は女性が約67%を占めていました。
年齢層を見ると、20歳代以下から70歳代以上まで幅広く、特に40歳代(約29%)と50歳代(約33%)が多く活躍している状況がうかがえます。
上記のデータは、必ずしも受験者全体の年齢分布を直接示すものではありませんが、実際に登録販売者として働いている方々の傾向として、子育てが一段落した世代や、キャリアチェンジを経て専門性を身につけたいと考える中高年層、そして若年層に至るまで、様々なライフステージの方が資格を活かして活躍していることを示唆しています。
「やってみたい」という気持ちがあれば、まずは挑戦してみる価値のある資格と言えるでしょう。
出典:
厚生労働省|登録販売者制度の取扱い等について、医薬品情報学|医薬品登録販売者の業務の実情と医薬品販売制度変更に対する意識調査
試験範囲と出題傾向
登録販売者試験は、厚生労働省が示す「試験問題の作成に関する手引き」に基づいて出題されます。試験科目は以下の5項目で、合計120問、試験時間は240分(午前・午後各120分)が一般的です。
| 試験科目 | 問題数 | 内容 | 対策方法 |
| 1、 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 20問 | 薬の基本的な性質、剤形、吸収・代謝、副作用、相互作用など、医薬品全般の基礎。 | 暗記だけでなく、なぜそうなるのかという理解が重要。 |
| 2、人体の働きと医薬品 | 20問 | 消化器系、循環器系、呼吸器系など、各器官の構造と働き、医薬品がどう作用するのかを学ぶ。 | 薬の作用機序と関連付けて覚えるのがコツ。 |
| 3、主な医薬品とその作用 | 40問 | 風邪薬、胃腸薬、アレルギー用薬など、具体的な医薬品の成分、効能効果、副作用、相互作用について学ぶ。 | 出題範囲が最も広い。成分名や特徴を正確に覚える必要がある。 |
| 4、薬事に関する法規と制度 | 20問 | 医薬品医療機器等法を中心に、登録販売者としての業務遂行に必要な法律や制度の知識を学ぶ。 | 改正点や通知なども注意が必要。 |
| 5、医薬品の適正使用と安全対策 | 20問 | 医薬品の正しい使い方、副作用が出た場合の対応、情報提供の仕方、濫用のおそれのある医薬品など、実践的な内容を学ぶ。 | 単なる暗記ではなく、具体的な事例を意識して学ぶ。
|
合格基準は、総出題数(120問)に対する正答率が7割以上(84問以上)であり、かつ、上記の試験項目ごと(5項目)の出題数に対する正答率が3割5分以上であること、この両方を満たす場合に合格となります。
つまり、全体で高得点を取れても、苦手な科目で足切りラインを下回ると不合格になるため、バランスの取れた学習が不可欠です。出題傾向としては、基本的な知識を問う問題が多く、手引きの内容をしっかり理解していれば対応可能です。
出典:
厚生労働省|登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和7年4月)、東京都保健医療局|令和7年度登録販売者試験について
登録販売者の就職先と働く場所

登録販売者の資格を活かせる職場は、年々多様化しています。主な就職先とその特徴は以下の通りです。
| 主な就職先 | 特徴 |
| ドラッグストア | 最も一般的な就職先。 医薬品だけでなく日用品も扱い、求人数が多い。 |
| 薬局 (調剤薬局併設含む) | OTC医薬品コーナーでの相談業務が中心。 薬剤師との連携が重要。 |
| コンビニエンスストア | 24時間対応可能な店舗での需要増。 比較的時給が高い傾向も。 |
| スーパーマーケット・ ホームセンター | 医薬品コーナー設置店舗での活躍。 |
| インターネット通販 (ECサイト運営企業) | 医薬品のネット販売における相談対応や情報提供。 |
これらの職場で、登録販売者は正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、ライフスタイルに合わせた多様な雇用形態で働くことが可能です。医薬品販売の専門家として、地域住民の健康を支える幅広いフィールドが広がっています。
出典:
厚生労働省|職業情報提供サイトjob tag「医薬品販売/登録販売者」、厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課|医薬品販売制度の変遷
ドラッグストア・薬局での活躍
ドラッグストアや薬局は、登録販売者にとって中心的な活躍の場です。
ドラッグストアでは、第2類・第3類医薬品の販売とカウンセリングはもちろんのこと、健康食品や化粧品、日用品の販売、レジ業務、商品の品出し・陳列、在庫管理、POP作成など、店舗運営に関わる幅広い業務を担うことが一般的です。購入される方の多様なニーズに応える総合的なスキルが求められます。
一方、薬局(特に調剤薬局に併設されたOTC販売コーナー)では、主に一般用医薬品の相談販売に特化した業務が多くなります。薬剤師と連携し、処方箋を持たない方へのOTC医薬品によるセルフメディケーション支援が主な役割です。
求人需要は、ドラッグストアが店舗数の多さや営業時間の長さから常に高い水準です。薬局においても、かかりつけ機能の強化やOTC医薬品のラインナップ拡充に伴い、登録販売者の専門性を求める声が高まっています。
実際、ドラッグストアでは店舗によって登録販売者のみで、薬剤師不在の場合もあるようです。
登録販売者の年収・給与
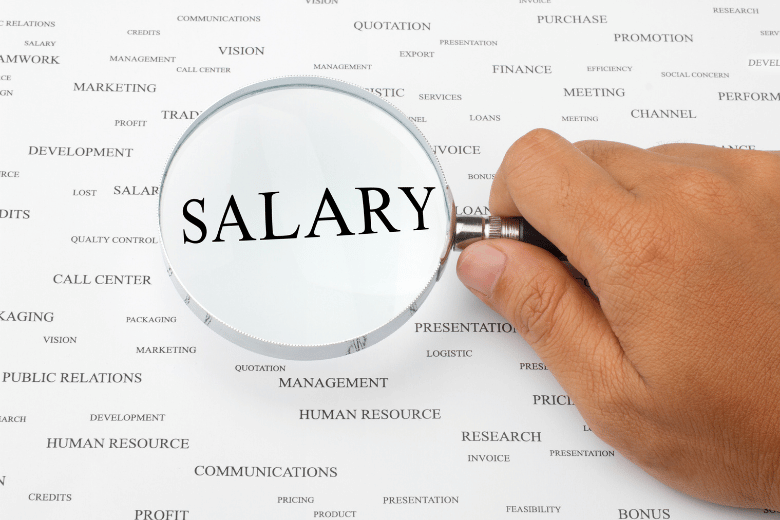
登録販売者の収入は、日本の平均年収と比較するとやや低い傾向にありますが、経験やスキル、勤務先の企業規模や業種、勤務地域によって大きく変動します。
登録販売者の年収・給与の主な変動要因は、以下のとおりです。
● 経験年数
● 勤務先の種類・規模(ドラッグストア、薬局、コンビニなど)
● 地域差
● 夜勤や休日出勤の有無
● 資格手当の額など
しかしながら、セルフメディケーション推進やドラッグストア等の多様化により、登録販売者の需要は安定しています。
雇用形態別の平均収入
登録販売者の収入は、雇用形態によって大きく異なります。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」に掲載されている「医薬品販売/登録販売者」のデータ(令和6年賃金構造基本統計調査の結果を加工)によると、平均的な賃金は以下の通りです。
【登録販売者の収入】
| 雇用形態 | 平均収入 |
| 正社員 | 全国の賃金(年収)369.4万円 |
| 短時間労働者 | 全国の1時間当たり賃金1,181円 |
このデータから、例えばパートタイムでフルタイムに近い勤務(1日8時間、月20日勤務と仮定)をした場合、単純計算で年収は約226万円(1,181円 × 8時間 × 20日 × 12か月)程度となります。
ただし、これらはあくまで全国平均の数値であり、実際には勤務先の企業規模、業種(ドラッグストア、調剤薬局、コンビニエンスストアなど)、店舗の売上規模、都市部か地方かといった地域差、個人の経験年数や能力、役職(店長、エリアマネージャーなど)によって、給与水準は大きく変動します。
また、賞与(ボーナス)の有無や支給額も年収に影響を与える重要な要素です。
出典:
厚生労働省|職業情報提供サイトjob tag「医薬品販売/登録販売者」、国税庁|令和5年分 民間給与実態統計調査
資格手当はいくら期待できる?
登録販売者の資格を取得すると、「資格手当」が支給されることが一般的です。これは、専門的な知識を持つ人材に対する評価の一つと言えます。
残念ながら、企業規模や業態別の資格手当に関する公的な集計データは現在のところありません。
しかし、一般的に言われている相場としては、正社員で月に5,000円から20,000円程度、パート・アルバイトの場合は時給に50円から数百円程度が上乗せされるケースが多いようです。
資格手当の額は、勤務先の企業の方針、店舗の規模や業績、地域、そして個人の経験や管理者要件(実務経験2年以上など)を満たしているか否かなどによって変動します。特に管理者要件を満たし、店舗管理者としての責任を担うようになると、より高い資格手当や役職手当が期待できるでしょう。
就職や転職の際には、基本給だけでなく、資格手当の有無や金額、その他の手当(役職手当、通勤手当など)、賞与の支給実績などを総合的に確認することが大切です。
\あなたに合った職場をお探しします!/
まとめ
本記事では、医薬品販売の専門家「登録販売者」について多角的に解説しました。
登録販売者は、2009年の法改正で誕生し、第2類・第3類医薬品の販売や情報提供を通じて地域医療に貢献します。薬剤師とは異なり、調剤は行えませんが、受験資格に制限がなく、多様な人材が活躍できる門戸の広さが魅力です。
仕事内容は、ドラッグストアや薬局を中心に、医薬品のカウンセリング販売から店舗運営まで多岐にわたります。セルフメディケーションの重要性が増す中、登録販売者の需要は安定しており、今後もますます地域住民の健康に貢献するでしょう。
よくある質問
登録販売者って難しいですか?
登録販売者の合格率は、昨今、40~50%程度を推移しています。数字だけで比べることはできませんが、受験資格に一切の制約のない点を考慮すると、比較的取得しやすい資格と言えるでしょう。
登録販売者とはどんな仕事ですか?
登録販売者の仕事内容は、医薬品を買う目的で来店した購入される方に対応をしながら、使用者の症状や状態を聞き出し、効果や副作用についての説明をして、適切な医薬品を選ぶ手助けをすることです。相談に応じ、使用方法についてもアドバイスします。

