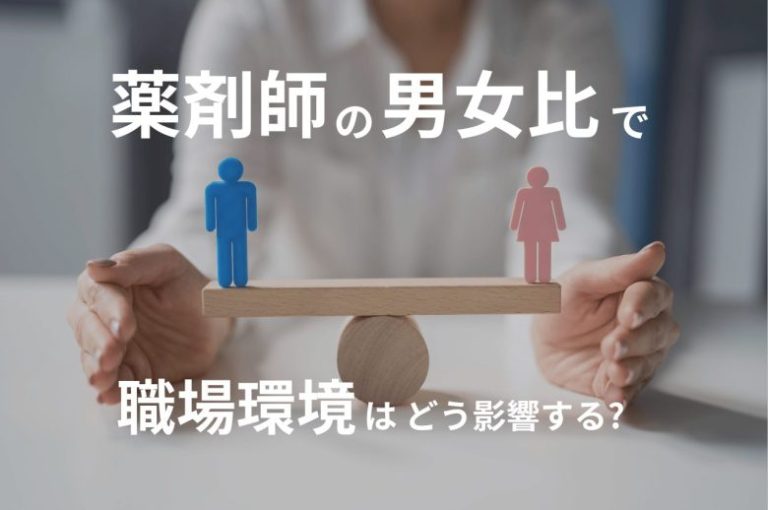薬剤師は女性が多い職業ですが、実際にどのくらいいるのか、具体的な数字などはご存じですか。
女性が働きやすいと言っても、極端な男女比だと、職場で困った事態に陥ることになるかもしれません。薬剤師としてのキャリアを考える場合には、薬剤師の置かれている医療環境や役割の変化にも、注意する必要があります。
この記事では、男女別薬剤師の人数、薬剤師として薬局や医療機関で働いている人の人数、男女比、薬剤師に女性が多い理由、薬剤師の男女比が偏ることによる職場への影響などについて、紹介します。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)【男女別】薬剤師として登録されている人数はどれくらい?
厚生労働省の調査によると、2022年12月31日現在、薬剤師数は、男性124,183 人(38.4%)、女性199,507人(61.6%)となっています。男女比はおおよそ4:6であり、女性の方が多い職業と言えます。
届出薬剤師数総計を前回と比べると1,708人、0.5%の増加です。また、人口10万対薬剤師数は259.1人で、前回に比べ3.9 人増加しています。
日本国内に在住し、薬剤師法第9条に基づいて届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象としており、届出経路は紙媒体(医療機関などに勤務)とオンライン(本人)の2つです。あくまで登録者の人数であり、勤務していない(もしくは一時的に働いていない)薬剤師の数も含まれています。また、どちらの経路でも登録していない薬剤師もいる可能性があります。
参照元:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
薬剤師として薬局や医療機関で働いている人の人数
勤務している施設別に、薬剤師数をまとめたのもが、以下の表です。
【施設別に見た薬剤師数】
| 2022年 | 対前回 | 人口10万対(人) | ||||
| 人数 | 構成割合(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 薬局 | 190,735 | 58.9 | 1,753 | 0.9 | 152.7 | 2.9 |
| 医療施設 | 62,463 | 19.3 | 860 | 1.4 | 50.0 | 1.2 |
| 介護保険施設 | 1,091 | 0.3 | 103 | 10.4 | 0.9 | 0.1 |
| 大学 | 4,902 | 1.5 | -209 | -4.1 | 3.9 | -0.2 |
| 医薬品関係企業 | 37,086 | 11.5 | -1,958 | -0.5 | 29.7 | -1.3 |
| 衛生行政機関または 保健衛生施設 | 6,927 | 2.1 | 151 | 2.2 | 5.5 | 0.1 |
薬剤師の勤務先として最も多いのは薬局で、全体の58.9%、190,735人が働いています。前回調査と比較すると1,753人(0.9%)増加しており、ニーズは着実に増えていると言っていいでしょう。
次いで多いのが医療施設で、62,463人(19.3%)が勤務しています。こちらも860人(1.4%)の増加です。
医薬品関係企業の項目では製薬企業やドラッグストアなどに勤務している薬剤師数を示していますが、37,086人(11.5%)、1,958人と減少しています。また大学(4,902人、1.5%)でも209人の減少が見られ、これらの分野での採用状況の変化が伺えます。
特筆すべき点としてあげられるのが、介護保険施設での薬剤師数です。人数は1,091人と全体の0.3%にとどまるものの、前回比10.4%増と最も高い成長率になっています。これは高齢化社会における介護分野での薬剤師ニーズの急速な拡大を反映しているものと言えるでしょう。
参照元:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
薬剤師として薬局や医療機関で働いている人の男女比
薬局や医療機関で働いている薬剤師を性別にみると、男性が前回に比べ1,240人(1.4%)増加の88,379人、女性は1,373人(0.8%)増加の164,819人で、男女比にすると約1:2です。
年齢階級別にみると、「30~39歳」が66,627人(26.3%)と最も多く、次いで「40~49歳57,645人(22.8%)となっていますが、これを性別にみると、男女とも「30~39歳」(男30.7%、女23.9%)が最も多くなっています。全体の登録者数の男女比率は4:6ですが、薬局や医療機関に限れば、1:2で女性が多く在籍していることが分かります。
これらのことから、男女とも新卒では薬局や医療機関以外に就職するけれども、30代までには転職し、これらの職場へ在職し続けている人が多いと考えても良いのかもしれません。また、数字としてはあげていませんが、年齢階級別構成割合は、女性では13.6~23.9%(~69歳)と男性の12.5~30.7%(~69歳)と比べると変動幅が小さく、これらの職場で女性の離職は少ないと考えられます。
薬剤師はよく「女性が働きやすい職業」と言われますが、そのことの一端を数字が示していると言っても良いかもしれません。
この統計資料は、あくまでも全国の薬局・医療機関のものなので、地域によっては違った状況であることも十分に予想できます。男性が多かったり、人手不足が深刻化していたりなど、女性ばかりの職場になるとは限りません。
参照元:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
薬剤師の男女別の給与目安
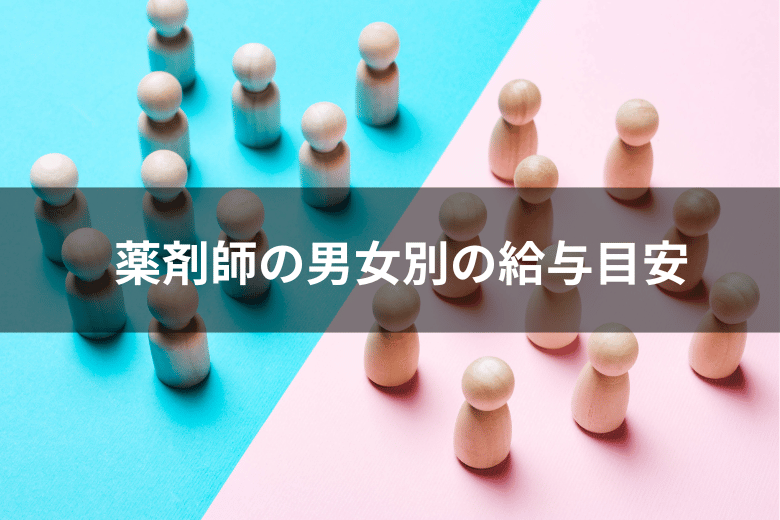
ここでは、厚生労働省の統計資料から解析した結果に基づいて、薬剤師の男女別の給与目安をお話しします。薬剤師の給与の特徴をあらわすために、年代別に示しています。併せて年収も載せているので、総合的に考える時の参考にしてください。
男性の場合
男性の年代別、薬剤師の月収と年収は以下のとおりです。年収は以下の式から計算しました。
【年収の計算式】
年収=毎月きまって支給する現金給与額*12+年間賞与その他特別給与額
【男性の年代別月収と年収】
| 年代 | 月収(万円) | 年収(万円) |
| 20~24歳 | 33.2 | 398.3 |
| 25~29歳 | 34.4 | 478.2 |
| 30~34歳 | 40.4 | 571.7 |
| 35~39歳 | 49.3 | 692.3 |
| 40~44歳 | 47.7 | 650.7 |
| 45~49歳 | 52.8 | 746.0 |
| 50~54歳 | 54.3 | 710.3 |
| 55~59歳 | 55.3 | 763.3 |
| 60~64歳 | 45.6 | 589.2 |
| 65~69歳 | 39.3 | 504.5 |
| 70歳~ | 35.5 | 470.8 |
最も高いのは55~59歳で55.3万円、45~59歳までは50万円以上という月収が続いています。定年となる60歳以降は減少し続けますが、70歳以上でも35.5万円以上という月収です。
一般労働者の賃金のピークが55~59歳で42.7万円であるのと比較すると、10万円以上、高いものになっています。
年代による月収上昇カーブを見ると、35~39歳で大きな伸びを示し、その後も着実に上昇を続けています。これは管理薬剤師としての経験や、病院薬剤部での管理職への登用などが影響していると考えてよいでしょう。
また、60歳以降も比較的高水準の月収を維持できているのは、医療機関での継続雇用制度の充実や、調剤薬局での豊富な経験が評価されているあらわれと言えます。このように、薬剤師は長期的なキャリア形成が可能な職種といえるでしょう。
参照元:e-Stat令和5年賃金構造基本統計調査「職種(特掲)、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」、「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」
女性の場合
女性の年代別、薬剤師の月収と年収は以下のとおりです。年収は以下の式から計算しました。
【年収の計算式】
年収=毎月きまって支給する現金給与額*12+年間賞与その他特別給与額
【女性の年代別月収と年収】
| 年代 | 月収(万円) | 年収(万円) |
| 20~24歳 | 27.8 | 334.2 |
| 25~29歳 | 34.4 | 467.1 |
| 30~34歳 | 38.3 | 536.9 |
| 35~39歳 | 40.2 | 578.8 |
| 40~44歳 | 39.6 | 589.8 |
| 45~49歳 | 37.3 | 526.2 |
| 50~54歳 | 48.3 | 675.2 |
| 55~59歳 | 49.6 | 695.8 |
| 60~64歳 | 42.3 | 559.8 |
| 65~69歳 | 55.8 | 716.3 |
| 70歳~ | 45.3 | 546.4 |
少し不思議ではありますが、最も高い月収は一般では定年と言われる年齢の60歳以降である65~69歳で、55.8万円です。また70歳以降でも45.3万円という数字です。
この年代になると、長期間薬剤師を続けてきた女性だけが勤務し続け、そのため経験年数に応じた月収を得ているものと思われます。女性一般労働者の月収のピークが50~54歳で、28.6万円であることと比べるとおおよそ2倍だと考えてもいいでしょう。
薬剤師という職業は、女性が働きやすい職業で、働き続ければ通常の約2倍の月収が得られると言っても良いかもしれません。
この値は全国調査の値なので、地域によってはこの値や傾向と異なる状況の場合もあるかと考えられます。あくまでも参考として、捉えてください。
参照元:e-Stat令和5年賃金構造基本統計調査「職種(特掲)、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」、「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」
あなたに合った職場をお探しします
薬剤師は女性が多い理由とは?
登録数も薬局や医療機関で働いている人も、女性の方が多いのが薬剤師です。それでは、薬剤師に女性が多いのはなぜでしょうか。
① 家庭と両立しやすい
② 産後・育休後も職場復帰しやすい
以下で、1つずつ、詳しく説明します。
①家庭と両立しやすい
女性が薬剤師を目指す理由の一つにあげられるのが、「家庭と両立しやすい」ということがあります。勤務先を選べば転勤や異動も少なく、勤務形態もシフト制や時短勤務など柔軟な働き方ができる職場がたくさんあります。また、夜間診療する病院以外では、基本的に夜勤がなく、日中勤務が中心です。
さらに、一般的なパートと比較すると時給も高い職種であることも魅力になっています。特に、保育園の送り迎えにも対応しやすい勤務時間を選べます。
②産後・育休後も職場復帰しやすい
薬剤師は国家資格であり、一度取得すれば生涯有効です。そのため、出産や育児で一時的にキャリアを中断しても、復帰後も同じ立場で働けます。
また、調剤業務や服薬指導など、基本的な業務内容は大きく変わりません。そのため、調剤薬局や病院でも育児休暇なども比較的スムーズに取得できる職場が多い傾向にあります。また、大手の調剤薬局では復帰してきた女性薬剤師に対して、少しでも早く仕事を再開できるように、研修制度を設けているところも多いようです。
近年では、患者さんへの服薬指導や医療スタッフとの連携など、コミュニケーション能力を活かせる業務も増え、女性ならではの細やかな対応力が評価されるようになってきました。地方の薬剤師会によっては、復職支援プログラムを設けているところもあります。
特に、妊娠・出産を経験した女性薬剤師は、妊婦や子育て中の患者さんの気持ちに寄り添った服薬指導ができるため、貴重な戦力として重宝される傾向にあります。また職場復帰した後、正社員ではなく、契約社員やパート、派遣なライフスタイルに合わせて働き方を変えても、一定以上の給与をもらえるというのもメリットです。
薬剤師の男女比が偏ることによる職場への影響
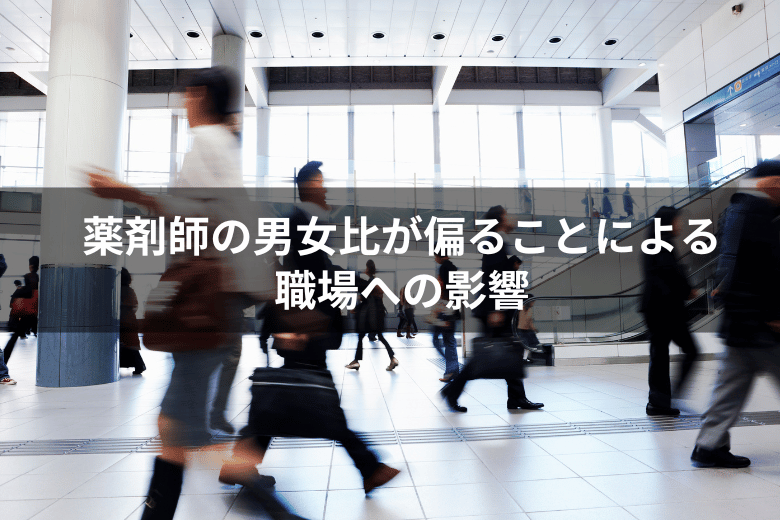
薬剤師の職場は、薬局や病院、製薬企業、官公庁など多岐に渡っていますが、女性が働きやすく、女性が多くなると、思わぬ状況が起きてしまうかもしれません。ここでは、薬剤師の男女比が偏ることによる職場への影響を2つ紹介します。
シフトが組みにくい
女性薬剤師が多く、パート社員が多い職場では、保育園の送迎時間に合わせた勤務時間を希望するなど、午後は早めに帰ってしまう傾向にあり、夕方閉店ごろはどうしても人手不足になりがちです。
そのため、フルタイムで働く薬剤師が夕方以降の業務に追われるなど、しわ寄せが来ることも多くなっています。繁忙期、閉店間際に忙しく、定時に帰れずに残業が慢性化してしまうこともあるかもしれません。
シフト調整に苦労する職場も少なくないことが予想でき、学校行事や子どもの病気など突発的な休暇にも対応する必要があり、またヘルプ薬剤師の確保も課題となります。
人材配置を充分に考慮して異動も検討してもらえる薬局であれば良いですが、個人経営の薬局では薬剤師の配置転換や補充採用も簡単ではありません。
管理職ポストに男性が偏りがち
性差による能力の差ではなく、女性は結婚や出産を機に退職したり、配偶者の転勤による転居が発生したりすることが多く、重大なポジションを任せにくいという考えは現在もまだ残っています。
管理職ポストを検討するときには、勤続年数も重要な評価ポイントです。企業や大手薬局では、管理薬剤師やエリアマネージャなどは男性薬剤師が多い傾向にあり、薬局や病院でも薬剤部長などの管理職には男性が就くケースが多く見られます。
男性薬剤師の場合、基本的には結婚や子ども誕生を機に辞めることは少ないので、昇進では有利に働きやすいです。重要なポジションで働きたい女性薬剤師には、このような男女の差を歯がゆく感じるかもしれませんが、近年では少しずつ解消されつつあるようです。
薬剤師の今後について
医療の高度化と地域包括ケアシステムの進展にともない、薬剤師の役割は大きく変化し続けています。6年制教育への移行後、全国で薬学部が新設され、一時は供給過剰が心配されましたが、依然として薬剤師不足の状態が続いています。このことの主な原因は、薬剤師業務が、物から人へ大きく変化したことでしょう。
現在、薬剤師の活躍の場は、従来の薬局や病院から在宅医療や介護施設へと拡大しつつあります。特に在宅医療では、多職種連携のもと、服薬指導や薬物療法の管理など、より専門的なケアが必要とされ、また、病院においては医療チームの一員として、より高度な臨床判断に関与する機会が増加しているというのが現状です。
このような環境変化に対応するには、専門性の向上が必要不可欠です。
薬剤師が参加する各学会では、がん専門薬剤師などの様々な認定資格制度を設けています。これらの資格は、5年以上の実務経験や実技研修など、厳格な要件が設定されており、高度な専門性を証明するものと言っていいでしょう。
治験や医薬品開発の分野でも、薬剤師の専門知識を活かした活躍が期待されています。
今後の薬剤師には、生涯学習を通じた継続的なスキルアップが求められ、特に、高齢化社会の進展にともない、在宅医療や地域医療における役割がさらに重要性を増すことが予想されます。また、医療のデジタル化への対応や、チーム医療における他職種との効果的な連携能力も必須となるでしょう。薬剤師として長期的にキャリアを築くためには、こうした社会のニーズに応える専門性と実践力を磨き続けることが重要です。
あなたに合った職場をお探しします
まとめ
男女別薬剤師の人数、薬剤師として薬局や医療機関で働いている人の人数、男女比、薬剤師は女性が多い理由、薬剤師の男女比が偏ることによる職場への影響などについて、紹介してきました。
2022年の厚生労働省の調査によると、薬剤師数は男性12.4万人、女性19.9万人で、男女比はおおよそ4:6でした。女性の方が多く、そして働きやすい職種だと言えますがですが、極端な男女比だと、シフト体制が組みにくいなど職場で困った事態に陥ることもあるかもしれません。薬剤師としてのキャリアを考える場合には、薬剤師の置かれている医療環境や役割の変化にも、注意する必要があります。