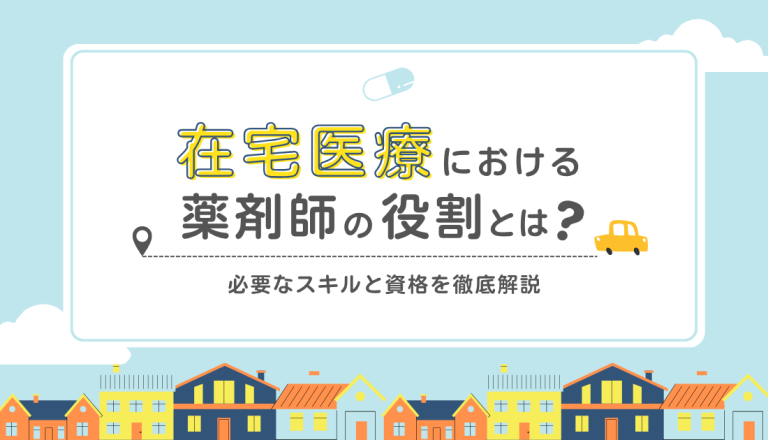「在宅薬剤師って?」「在宅薬剤師の仕事内容や役割・必要なスキルを知りたい…」と考えている薬剤師の方もいるかもしれません。
在宅薬剤師とは、在宅医療や在宅介護を受けている患者の自宅や入居先を訪れ、業務をする薬剤師のことです。
高齢化が進む日本では、急速に在宅医療のニーズが高まっています。特に高齢者は複数の薬剤を飲んでいる場合も少なくないため、在宅医療における薬剤師の役割はとても重要です。
この記事では、在宅薬剤師の概要と意義、在宅薬剤師の必要性、在宅薬剤師の仕事内容と役割、在宅薬剤師に必要なスキルと資格について、ドラッグストア勤務経験のある元病院薬剤師が解説します。この記事を読めば、在宅薬剤師の仕事内容や役割・必要なスキルと資格が分かります。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)在宅薬剤師の概要と意義

ここでは、在宅薬剤師の概要や存在意義について説明します。
在宅薬剤師とは
在宅薬剤師とは、在宅医療・在宅介護を受けている患者宅を訪問して業務をする薬剤師のことです。
一般的に薬剤師は、患者が持ってきた処方箋を基に、その場で調剤・服薬指導をします。しかし、在宅薬剤師は患者宅を訪問して薬剤を提供・管理するほか、健康についての相談に応じる場合もあるという点が大きく違います。
在宅薬剤師の勤務先は保険薬局です。調剤薬局で外来調剤と並行しつつ在宅業務を実施していることがほとんどですが、最近は在宅専門薬局も増えています。なお、調剤薬局が「在宅患者訪問薬剤管理指導」に係る届出をしており、患者が介護認定を受けている場合の報酬の請求先は、介護保険です。
そうでない場合は、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を医療保険に請求します。対象患者が介護認定を受けていれば、医療保険より介護保険が優先して利用されるので、「居宅療養管理指導費」を算定します。
在宅医療における薬剤師の意義・役割は?
高齢化の影響で在宅医療のニーズが高まり、その中で薬剤管理や服薬指導を担う薬剤師への期待が集まるようになりました。薬剤師が在宅医療に関わると、社会的入院から在宅療養への移行が促進されるので、患者のQOLが向上します。在宅薬剤師は患者の生活に踏み込んで健康をサポートします。
たとえば飲み忘れ予防対策でも、患者の日常生活や行動について丁寧に耳を傾け 、それに合わせた指導を実施するのです。かかりつけ薬剤師よりも身近な存在で、家族の負担を減らす効果も担います。
薬剤師が在宅医療に関与する意義は以下のとおりです。
● 看護・介護職がやむをえず薬に関わっている現状を改善する
● 多職種連携と相互の専門性を発揮して適正なサービスを提供できる
在宅患者訪問薬剤管理指導などにより改善される飲み残し薬剤費の粗推計は約400億円とも言われ、トータルコストが削減でき、在宅医療サービスの質が向上します。
また、在宅を担当する医師の負担軽減も可能です。在宅薬剤師が在宅医療に関与することでできる医師の業務負担軽減は以下のとおりです。
● 薬学的管理指導に基づく患者状況の確認とフィードバック
● 患者の療養状態に応じた用法・用量の調節や処方変更の提案
● 服薬状況(適正使用)、副作用などの確認
● 患者からの相談応需と関係職種への連絡などの分担
在宅薬剤師は薬剤師の専門性を発揮できる業務といえます。
医療チームの中での薬剤師のポジション
在宅医療には、医師や看護師、ケアマネジャーなど多様な職種が関わっています。薬剤師が加わることで、医療の質、安全性の向上が期待されます。
たとえば、看護師から便秘や吐き気などの症状の報告があった場合、単に下剤や制吐剤を追加するのでは、薬が増える一方です。薬学的なアセスメントをおこない、不要な薬を整理したり、副作用の少ない代替薬を提案したりすることができれば、医療の質も、患者のQOLも向上するでしょう。
このように、在宅医療のチームに薬剤師がいることで、より安全で効果的な薬物療法を目指せるのだという点を意識し、専門性を発揮していくことが重要です。
在宅薬剤師の必要性

在宅医療へのニーズが高まる中で、大きくなってきたのが薬剤師への期待です。薬剤師は患者の生活に寄り添うことで、QOLの向上に貢献できます。在宅薬剤師が生まれた背景には、どんな要因があるのでしょうか。
ここでは、在宅薬剤師の必要性について、解説します。
在宅医療患者は増加している
在宅医療制度を活用する患者数は増加しています。令和2年の厚生労働省の調査では、在宅医療を受けた推計外来患者数はおよそ17万3600人でした。約20年前の平成11年と比較すると、約2.5倍です。また、その中で65歳以上の患者数は約16万人でした。全体の約92%の利用が高齢者によるものです。
在宅医療を利用する患者が増加すると、必然的に在宅での薬物療法の頻度も多くなります。そのために在宅医療にかかわれる薬剤師への必要性が高まってきているのでしょう。
高齢化・社会のニーズ変化の影響も
総務省の「令和4年版高齢社会白書」によると、65歳以上人口は3,621万人で、総人口に占める割合も28.9%でした。白書では今後も65歳以上人口の増加傾向は続き、令和24年に3,935万人でピークを迎えると推測しています。
このような流れの一方で、社会のニーズは変化しています。従来病気の治療は入院でという考え方の人が多くいましたが、自宅で療養生活を送りたいと考える人が増えてきました。「病気になっても住み慣れた自宅で過ごしたい」「最期まで家族と一緒に過ごしたい」などという人が多くなってきているのです。
そのため、在宅医療を必要とする人も多くなってきています。在宅医療は、慢性期の患者や終末期ケアを希望する患者に対して、生活の質に重きを置いた医療でもあります。
病気でも最期の時になっても従来の生活をできるだけ保ちたいというニーズに応えるために、在宅医療の必要性は高まってきています。
病床数削減による在宅医療へのシフト
国の示している「地域医療構想」では、医療機能を集約化し、急性期病床や慢性期病床の削減、および回復期病床の増床が打ち出されており、実際に平成29年の6.59万床から、令和7年末までに6.02万床へと、病床数の削減は進んできています。
看取りの場として自宅を希望している方の割合も多いことから、在宅医療へとシフトさせる考えです。
安心して在宅療養をおこなえる環境を構築していくため、在宅薬剤師のニーズは今後も高まっていくと思われます。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)在宅薬剤師の仕事内容および役割

ここでは、在宅薬剤師の仕事内容と求められる役割を解説します。
在宅薬剤師の仕事内容
在宅薬剤師の仕事内容は、基本的には通常の薬剤師と大きくは違いません。「業務をどこで行うのか」が違うという認識で問題はないでしょう。ただし、患者宅に訪問するからこそ生じる役割もあります。
患者の状態によって医師のように接したり、ケアマネジャーなどへ情報を提供し共有したりすることもあるでしょう。また患者や家族とコミュニケーションを密に取ることで、薬の効果や副作用についての情報を引き上げたり、それを元に医師へ適切な処方薬を提案したりなどその業務範囲は多岐に渡っています。
在宅薬剤師の仕事内容は、以下のとおりです。
● 患者宅への医薬品・衛生材料の供給
● 薬歴管理(薬の飲み合わせの確認)
● 服薬の説明(服薬方法や効果などの説明、服薬指導・支援)
● 服薬状況と保管状況の確認(服薬方法の改善、服薬カレンダーなどによる服薬管理)
● 副作用などのモニタリング
● 在宅担当医への処方支援(患者に最適な処方(剤型・服用時期などを含む)提案)
● 残薬の管理、麻薬の服薬管理と廃棄
● ケアマネジャー などの医療福祉関係者との連携・情報共有
● 医療福祉関係者への薬剤に関する教育
在宅薬剤師は処方箋の内容を確認して調剤をし、患者宅に薬剤を持参して、薬剤の提供や服薬指導をします。
薬剤管理は、高齢者や認知機能が低下した患者には非常に困難なものです。しかし誤飲や過量服用などにもつながりかねません。在宅薬剤師は必要に応じて、服薬カレンダーなどを使うこともあるでしょう。
服薬に関してだけでなく、健康状態の管理にも関与します。薬剤の副作用のモニタリングをし、疑いがある場合には医師に報告もしくは処方変更を提案します。また、ケアマネジャー などに薬剤の使い方や注意事項などを教育・助言することも在宅薬剤師の業務のひとつです。
医薬品・衛生材料の提供と管理
在宅患者へ医薬品を提供する際も、医師の発行する処方箋に基づいた調剤が基本です。在宅医療では患者宅へ訪問する点が特徴ですが、自宅での管理方法についても、温度や湿度が適切かなど、必要に応じて指導をおこないます。
また、薬局では、以下のような衛生材料も扱っています。
● 消毒剤
● 自己検査用血糖測定用品
● 導尿バック
● ガーゼ、テープ類
● 弾性ストッキング
医薬品も衛生材料も、適正な方法で保管し、期限の管理などが必要です。
服薬指導と薬学的管理
在宅医療でも、服薬指導はメイン業務の1つです。服用する薬に変更があった場合には、しっかりと説明をおこない、患者本人や家族から理解を得る必要があります。また、相互作用や用量は問題ないか、副作用は出ていないかなど、薬学的な管理も欠かせません。
高齢患者の中には、認知機能低下がある方も多く、コンプライアンス不良、拒薬など、服薬指導が難しいと感じる方もいるでしょう。
拒薬をする原因として、薬を不要だと思っているという場合も多いですが、嚥下機能に問題があり服用しにくいから拒否している場合もあります。患者の残存能力を把握し、適切な支援を考えることも、大切な業務です。
残薬管理と適正使用の推進
頻繁に飲み忘れる、自己中断を医師に隠して処方をもらい続けている、頓服薬の使用回数が少ないにも関わらず処方され続けているなど、自宅に残薬を抱えている患者は多いです。
薬剤師が残薬確認をおこない、残薬が生じた理由を踏まえ処方変更の提案をしたり、管理しやすいよう一包化したりすることで、年間数百億円規模の医療費削減につながると推察されます。
在宅薬剤師が、患者の自宅に訪問するからこそできる業務といえるでしょう。残薬の確認や整理、適正使用の推進は、国民皆保険の維持のためにも重要な業務です。
在宅薬剤師に求められる役割
在宅薬剤師の役割は、薬物療法や薬などの専門知識で、患者に最も効果的で安全な薬物療法を提供することです。
在宅薬剤師の役割を以下に挙げてみました。
● 服薬指導・服薬管理
● 副作用や飲み合わせの確認
● 健康相談への対応
● 他職種との連携
在宅薬剤師は患者との距離が近いので、コミュニケーションの中でちょっとした情報を得たり、日常生活の中で患者の変化に気づいたりすることがあります。このような情報や気づきを、他職種のスタッフと共有し連携して、QOLを上げたり薬物療法の変更につなげたりすることも大きな役割と言えるでしょう。
薬物療法の安全性確保における薬剤師の重要性
高齢者の場合、さまざまな疾患に対して多剤併用が必要となるケースが多く、副作用マネジメント、用量調節など、丁寧な薬学的な管理が必要です。
たとえば、ある薬剤の副作用で不眠が生じ、その対策のために睡眠薬が増え、その副作用のめまいのために薬が処方され…というように薬剤が次々に増えていくことを「処方カスケード」と呼びます。処方カスケードを是正することで、患者の負担軽減、安全性の向上、医療費の抑制といったさまざまな効果が得られるでしょう。
口から薬剤を服用するのが難しい方には、胃瘻などから「簡易懸濁」で投与していることもあります。簡易懸濁できる薬剤かの確認、できない場合の代替薬の提案なども、安全性・有効性を担保する上で重要な業務です。
在宅薬剤師に必要なスキルと資格

在宅薬剤師になるための資格要件は、薬剤師であることの他にはありません。しかし、患者や患者家族と接する機会が多く、他職種との連携も欠かせないため、コミュニケーションスキルは必要になってきます。
コミュニケーションスキルの重要性
在宅薬剤師にとって重要なのは、「患者の状況に合わせて薬剤管理や服薬指導ができているか」です。
患者とより深く接する在宅薬剤師だからこそ、生活スタイルや環境を考えた総合的な判断とアドバイスができるのです。そのため、薬剤師としての知識だけではなく、経験がなくてはなりません。
また、在宅医療はチーム医療で、医師をはじめ、訪問看護師、歯科医師、ケアマネジャー 、ホームヘルパーなどと接しながら、患者をサポートする必要があります。患者の状態把握のためにもコミュニケーション能力は必要です。患者から薬に関する困りごとを聞き出し、どうすれば解決できるのかを考えます。
たとえば、薬が飲めないことを隠している患者の例を考えてみましょう。
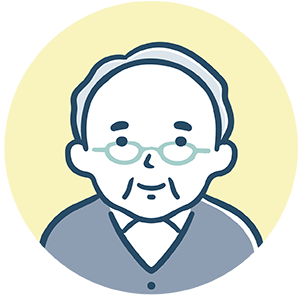
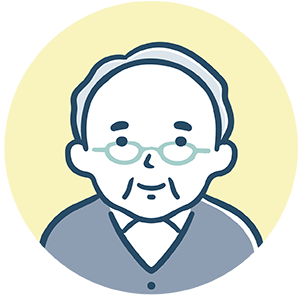
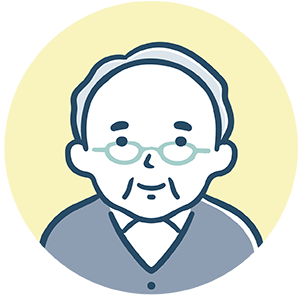
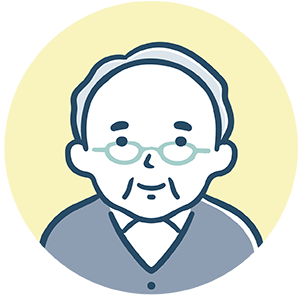
在宅で長く患者と関わるからこそ、患者の性格や生活環境がわかります。また、医師や看護師、ケアマネジャーなど他の職種から患者の状態を聞いていれば、状態に合った剤形変更をおこなうことも可能です。
在宅医療に役立つ認定資格
在宅医療に取り組む上で「在宅療養支援認定薬剤師」の資格があるとよいでしょう。在宅療養支援認定薬剤師とは、在宅療養支援に関する知識・技能・態度を備えた薬剤師のことで、日本在宅薬学会の在宅療養支援認定薬剤師制度の試験に合格することで得られる資格です。
新規の在宅療養支援認定薬剤師の申請要件は、以下のとおりです。
● いずれかの資格を取得していること:薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師、日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師
● 所定の研修講座受講により40単位以上の研修単位を取得していること
● 日本在宅薬学会主催の学術大会参加証の写しの提示
● バイタルサイン講習会受講の修了証の写しの提示
● 所定の様式による5事例の事例報告書の提出
● 認定試験に合格すること
認定試験は年に1回、筆記試験と面接試験があります。認定期間は3年間で、更新のためには新規の時とほぼ同じ要件があります。在宅薬剤師の仕事をずっと続けたい人や極めたい人は、認定を受けて在宅療養支援認定薬剤師になることを検討してみるもの良いでしょう。認定を受けていることが患者や家族からの信頼につながる可能性もあり、自分のやる気の維持にもつながるでしょう。
そのほか、次のような資格も在宅医療の現場では役立ちやすいです。
多くの疾患を抱えがちな高齢者に対して包括的な薬剤的管理や指導をおこない、QOLの維持・向上に寄与できることが求められます。取得には、10症例の提出、実技実習の受講などが必要です。
● 緩和薬物療法認定薬剤師
近年は、在宅療養をされるがん患者も増えてきました。医療用麻薬をはじめ、疼痛コントロール、症状緩和に精通した薬剤師は、ニーズが高いです。
● 日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師
褥瘡の処置や治療における専門家として、薬剤師のほか、医師や看護師、理学療法士なども取得できる資格です。
在宅薬剤師は不可欠な存在

在宅医療を受ける患者の多くは高齢者です。複数の疾患を抱え、服用する薬剤も多岐にわたっています。
在宅薬剤師が患者宅を訪問し、薬物療法を支援すると、適切な薬物治療の継続・維持が可能です。服薬状況の把握、副作用のモニタリングなど、薬剤師ならではの専門的視点から、患者のQOL向上に努めます。また患者家族の負担軽減にもつながるでしょう。
また、医療従事者間での連携を図ることで、患者の状態変化に沿って情報共有を行えば、地域全体での患者ケアの質を高めることができます。
治療の多くに薬物が関与していることを考えると、在宅医療では薬物療法の管理が重要な課題で、在宅薬剤師はその中心的な役割を担っているといえます。
患者の生活を支え、安全で適切な薬物治療を提供する役割の在宅薬剤師は必要不可欠な存在なのです。
在宅薬剤師のメリット
在宅医療に薬剤師が関わることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。さまざまな観点からいくつかお伝えします。
患者にとっては、安全性やアドヒアランスの向上がメリットとなるでしょう。薬剤師が副作用のモニタリングや減薬・用量調整をおこなうことで、安全で効果的な薬物療法を受けることが可能です。
また、患者の生活を実際に理解した上で、服薬タイミングの調整、剤形変更などの提案が受けられるため、より服薬しやすくなると考えられます。
さらに、薬剤師が関わることで、在宅医療を担う医師や看護師の負担を軽減し、業務の効率化や質の向上を目指すことができます。
財政的なメリットも大きいです。薬剤師や看護師などのコメディカルスタッフの活用やオンライン診療を進めることで、在宅医療費を年間3,000億円抑制できると推計されました。
在宅薬剤師が直面する課題
在宅医療の現場では、望まない救急搬送や入院を避け、自宅で療養を続けるため、「時間外の対応」が求められるシーンが多くなります。
事前処方や予測指示には限界があり、時間外の処方への対応をゼロにはできません。24時間対応するためには、各調剤薬局の人員だけでは賄いきれないというのが現状です。人員不足を補う方法として、複数の薬局で協力して時間外対応にあたる薬局間地域連携を取り入れているところも増えてきました。
また、患者宅への移動時間が長く効率が悪くなりがちな点、調剤報酬点数が低く採算が合わない点なども、今後の課題です。最適な訪問ルートやスケジュールを自動作成するプラットフォームを使用するなど、DX化が求められます。
在宅薬剤師のキャリアパスと将来性
今後、地域包括ケアシステムを構築し在宅での療養・看取りなどを進めていく上で、薬剤師が在宅医療へより深く関わっていくことが求められてきます。
多数の疾患を抱えた患者、身体機能の低下した患者に対し、一人ひとりに最適化された安全な薬物療法を提供するためには、薬剤師の介入が必要不可欠です。
麻薬の管理や輸液の調製、在宅医への処方提案など、期待される役割はどんどん増えていくと考えられます。在宅医療は今後もニーズが高く、調剤薬局が避けて通れない業務となるでしょう。
「在宅療養支援認定薬剤師」の資格が作られたことからもわかるように、専門性の高い仕事です。できるだけ早い段階から経験を積んでいくことで、淘汰されない薬剤師になることができるのではないでしょうか。
よくある質問
在宅医療で薬剤師は何をするのですか?
処方箋に基づいた調剤、患者や家族への薬の提供や服薬指導が主な業務です。訪問診療に同行するなどして処方提案をおこなったり、患者の生活に合わせた管理方法の提案をおこなったりする点は、在宅薬剤師の特徴と言えます。
薬剤師が在宅訪問をしてくれる条件は?
病気や障がいなどによって通院や来局が困難な方、自宅での薬の使用や管理に不安のある方などで、医師がその必要性を認めて薬剤師に訪問を指示した場合に、在宅訪問をおこなうことができます。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)まとめ
在宅薬剤師の概要と意義、在宅薬剤師の必要性、在宅薬剤師の仕事内容と役割、在宅薬剤師に必要なスキルと資格について、解説してきました。
在宅薬剤師は、在宅医療や在宅介護を受けている患者の自宅や入居先を訪れ業務をおこなう薬剤師のことで、高齢化が進んでいる日本において、急速にニーズが高まっています。高齢者は複数の薬剤を飲んでいる場合も少なくないため、在宅医療における薬剤師の役割はとても重く、多くのことが期待されています。
在宅薬剤師には薬剤師であること以外の要件はありませんが、患者から情報を聞き出して的確にアドバイスする必要があるので、実務経験とコミュニケーション能力は必要です。長く続けたい人や極めたい人は日本在宅薬学会の在宅療養支援認定薬剤師になることを検討してみるもの良いでしょう。