「AIやIT化によって薬剤師の仕事が減るって本当?」「薬剤師はどうキャリアアップすればいいの?」と考えている薬剤師の方もいるかもしれません。
AIやIT化によって薬剤師の業務負担が軽減される可能性はあります。しかし、薬剤師に関わる環境も変化するので、働き方や求められる役割も変わっていくでしょう。柔軟な視点を持ち続け、時代の変化に適応する力があれば、必要以上に悩むことはないでしょう。
この記事では、薬剤師の職場別将来性、環境の変化、注目されている動向、今後仕事がなくなるかどうか、キャリア形成する方法について、ドラッグストア勤務経験のある元病院薬剤師が解説します。
この記事を読めば、薬剤師の将来性や業界の動向、キャリア形成のために身につけるべきスキルが分かります。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)【将来性】薬剤師は今後仕事がなくなる?

今まで薬剤師の環境の変化や注目されている動向について、解説してきました。しかし、「薬剤師の仕事がなくなる」という話を聞いた方も少なくないでしょう。ここでは、「薬剤師の仕事がなくなる」と言われる理由について解説します。
薬剤師の仕事がなくなると言われる主な理由
薬剤師の将来性に不安を感じる方が増えている背景には、いくつかの複合的な要因があります。
最大の要因は、AIやICT技術の目覚ましい発展です。調剤の自動化や医薬品情報管理システムの高度化により、従来の「対物業務」が機械に取って代わられるとの見方が広がっています。
また、薬学部の新設に伴う薬剤師数の増加により、将来的な飽和状態が懸念されている点も不安材料の一つです。
さらに、国の医療費抑制政策による薬価の引き下げや調剤報酬改定の厳しさが増すことは、薬局経営を圧迫し、結果的に薬剤師の雇用環境に影響を与えるのではないかと考えられています。
こういった薬剤師を取り巻く状況の変化が、薬剤師の仕事が「なくなる」と言われることにつながっています。
薬剤師の有効求人倍率の推移
厚生労働省の「一般職業紹介状況」によると、薬剤師を含む専門職の有効求人倍率は、以下の表のように依然として高い水準を維持しています。
【医療専門職の有効求人倍率(パート含む常用)】
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 2.49 | 1.91 | 2.04 | 2.18 | 2.11 |
新型コロナウイルスの影響による一時的な低下もありましたが、その後は回復基調にあり、2024年度は2.11倍です。これは求職者1人に対し2件以上の求人がある売り手市場を示しています。
しかし、長期的には薬剤師数の増加により、この状況が永遠に続くとは限りません。高い倍率が、必ずしも個々の薬剤師の将来を保証するわけではないという認識を持つことが、今後のキャリアを考える上で重要になります。
参照元:
e-Stat一般職業紹介状況(職業安定業務統計)「職業別労働市場関係指標(実数)(平成21年改定)(令和4年4月~)」、e-Stat一般職業紹介状況(職業安定業務統計)「職業別労働市場関係指標(実数)(平成23年改定)(平成24年3月~)」
処方箋の電子化とオンライン診療の影響
処方箋の電子化とオンライン診療の普及は、薬剤師の働き方に大きな変化をもたらしています。
電子処方箋は、紙の処方箋の受け渡しや入力作業を不要にし、業務を大幅に効率化します。このことで薬剤師は調剤過誤のリスクを減らせ、患者への服薬指導など、より専門的な業務に時間を割けるようになるのです。
また、オンライン診療の普及はオンライン服薬指導の需要を高め、場所に縛られない働き方を可能にしました。将来的には、患者の医療情報が一元化され、より質の高い薬学的管理を提供できる体制が整うと期待されています。
薬剤師は今後飽和状態になると予想されている
厚生労働省の調査によると、薬剤師の有効求人倍率は2021年2月の時点で1.89倍、2022年10月時点で2.07倍でした。現状、薬剤師の求人数は横ばいと考えられます。
出典:令和3年10月 一般職業紹介状況(厚生労働省)、令和4年10月 一般職業紹介状況(厚生労働省)
ただし、厚生労働省は2020年から2025年にかけて、投薬対象者数が11.3億人から10.9億人に減少すると予測しています。
日本の総人口の減少にともなって投薬対象者が減ることもあり、今後薬剤師は飽和状態になると考えられます。
AIを使うことで業務負担が軽減される可能性がある
AIの導入は、薬剤師の仕事を奪うものではなく、むしろ業務負担を軽減し、専門性を高めるための強力なツールとなります。
例えば、調剤監査支援システムや医薬品の在庫管理、薬歴の自動入力補助といった定型業務はAIが得意とする領域です。定型業務をAIに任せると、薬剤師はより付加価値の高い対人業務、すなわち患者一人ひとりの状態に合わせた丁寧な服薬指導や、医師への積極的な処方提案に集中できるようになります。
人間にしかできないきめ細やかなコミュニケーションや複雑な判断こそ、今後の薬剤師に求められる中核的な役割となるでしょう。
医療費適正化のための薬剤費抑制策
国の医療費適正化政策は、薬剤師を取り巻く環境にも大きな影響を与えました。
定期的な薬価改定による薬価の引き下げや、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進は、薬局の利益率に直接的な影響を及ぼします。この流れの中で、薬局経営は厳しさを増し、薬剤師にも変化が求められるようになりました。
薬剤師は単に薬を渡すだけでなく、患者にジェネリック医薬品の有効性や安全性を丁寧に説明し、不安を解消して切り替えを促すなど、医療費削減に貢献する役割が重要になってきたのです。
これは、薬剤師の職能をより社会貢献に繋げる機会とも言えるでしょう。
人口動態の変化による需要減少
我が国の人口は近年減少の局面を迎えており、2070年には総人口が9,000万人を割り込み、現在の約70%にまで減少すると推計されています。そのため長期的な医療需要が減少し、その影響で薬剤師の需要も低下するのではないかと危惧されています。
また、合計特殊出生率が人口置換水準を下回る状態が続いており、生産年齢人口の減少が避けられません。この傾向が続けば、薬剤師の労働力不足に陥る可能性があります。さらに、労働力人口の減少に伴い、薬局や病院経営の採算が悪化すれば、薬剤師の雇用が削減される可能性もあります。
しかし、人口減少傾向の中でも高齢化は進むので、むしろ薬剤師の需要は高まるとの見方もあります。需給のアンバランスへの対応が課題となりますが、社会保障を支える上で薬剤師の役割は重要です。
人口動態の変化に伴い、薬剤師の働き方や求められる役割も変わっていくでしょう。薬剤師一人ひとりが、柔軟な視点を持ち続け、時代の変化に適応する力が求められます。
薬剤師の仕事は本当になくなるのか?
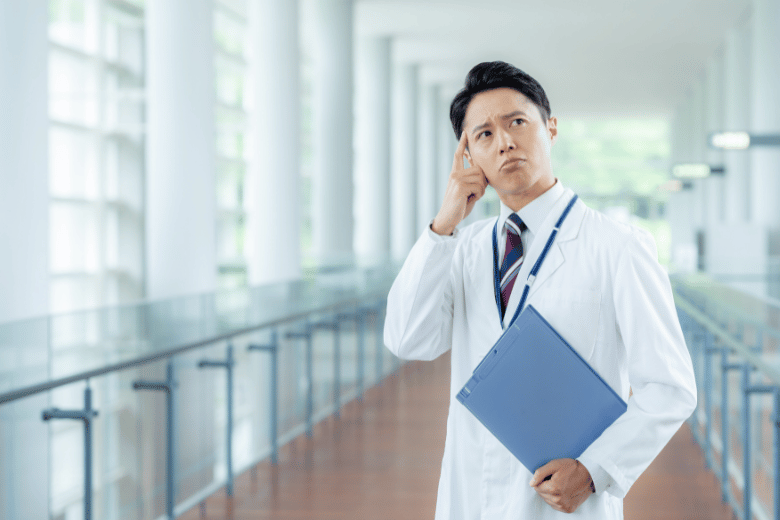
結論から言えば、薬剤師の仕事が完全になくなる可能性はとても低いと言ってよいでしょう。
確かにAIやICTの進化により、調剤や在庫管理といった対物業務は自動化が進むでしょう。しかし、薬剤師の本来の価値は、そこから先の対人業務にあります。
例えば、患者の表情や声色から副作用の兆候や服薬への不安を察知し、個別に対応することや、複数の薬の相互作用を評価し、医師に疑義照会するといった複雑な判断は、現在のAI技術では代替できません。
むしろ、定型業務をAIやICTに任せることで生まれた時間を活用し、在宅医療への参画したりセルフメディケーションを支援したりといった、より専門性を発揮する場面が増え、薬剤師の将来性は新しい形で広がっていくと考えられます。
AIに代替される業務と代替されない業務
AIによって代替が進む業務は、主に定型的でデータに基づいた判断が可能な「対物業務」です。具体的には、処方箋のデータ入力、ピッキング(数量を揃える作業)、医薬品の在庫管理・発注、薬歴の要約作成などがあげられます。
一方、代替されにくい業務は、コミュニケーション能力や倫理観、個別性の高い判断が求められる「対人業務」です。
副作用のモニタリング、複雑な判断が必要な疑義照会、患者の生活背景を考慮した服薬指導、多職種との連携、精神的なケアなどは、人間である薬剤師だからこそ担える重要な役割です。
対人業務への転換と専門性の発揮
今後の薬剤師には、対物業務から対人業務への大胆なシフトが求められます。
厚生労働省が掲げる「患者のための薬局ビジョン」でも、かかりつけ薬剤師・薬局として、地域住民の健康を積極的に支援する役割が期待されています。
具体的には、患者の服薬情報を一元管理し、24時間相談に応じる体制を整えたり、健康サポート薬局としてセルフメディケーションを推進したりする業務です。
これらを実現するためには、高度な薬学知識はもちろん、患者や他職種と円滑に連携するための高いコミュニケーションスキルが不可欠となります。
参照元:厚生労働省『「患者のための薬局ビジョン」~「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ~ を策定しました』
薬剤師の将来性について【職場別】

薬剤師の将来性は、働く場所によっても違いが出てくるでしょう。ここでは、薬剤師の主な就業場所の4つの職場別に薬剤師の将来性について解説します。
調剤薬局
自分のスキルアップに努め、さまざまな変化に対応できる薬剤師であれば、調剤薬局で働いた場合でも将来は明るいでしょう。
薬剤師に求められるものは、専門性が高く、多様化、細分化されてきています。たとえば、高齢化社会の到来で在宅医療への需要が高まっていますが、薬剤師は在宅医療の場でも職能を充分に発揮し、キーパーソンとなるでしょう。
調剤薬局の店舗数は増加傾向にあり、厚生労働省の調査によれば、2019年時点で約6.1万軒(宮城県、福島県の一部は除く)でした。
薬剤師は飽和状態になると予想されているため、そもそもAIができるような仕事にしかできない薬剤師は危ういと言えます。求められる人材であるためには、常にブラッシュアップする努力が必要です。
ドラッグストア業界の成長と薬剤師需要
2014年に13,069件だったドラッグストアの店舗数は、2019年には16,422件まで伸びました。商品販売額も4.9兆円から6.8兆円まで伸びています。
新型コロナウイルスの影響で予防意識が高まり、セルフメディケーションを実践するために、ドラッグストアの利用が増加傾向にあるのも予想できます。これらのことから、ドラッグストア業界における薬剤師の需要は今後ますます高まっていくでしょう。
また、調剤医薬品の販売額も3,451億円から5,524億円まで増加しています。
調剤併設型の増加も見られるので、登録販売者にはできない業務も増え、一定数の薬剤師が必要になります。ただし、幅広いジャンルで活躍するために、漢方薬関係やサプリメントアドバイザーをはじめとした資格を取ったり、接遇スキルを高めたりという、付加価値を高める努力も必要になるでしょう。
ドラッグストア業界は、M&Aを繰り返しながら市場規模を拡大し続けています。店舗数・売上高ともに右肩上がりの成長で、薬剤師の新たな活躍の場となっています。セルフメディケーション意識の高まりから、OTC医薬品に関する専門的なアドバイスを求める生活者も増加し、薬剤師の需要は依然として高い状況です。
食品や日用品も扱うため、景気や診療報酬改定の影響を受けにくい安定した経営基盤も魅力であり、将来性のある職場の一つと言えます。
参考:政府統計の窓口|ドラッグストア販売 商品別販売額等及び前年比増減率
病院
病院で働く薬剤師(病院薬剤師)の将来は比較的明るいといえるでしょう。
終戦直後のベビーブームに生まれた世代が、すべて後期高齢者になる時期を控えているからです。2025年には、75歳以上の人口は全人口の約18%、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%になると厚生労働省は推計しています。しかし、患者が増えるということだけで、薬剤師の地位が安泰とは言い切れません。
医療費は国の財政を圧迫しているという現状に変化はないので、病院によっては経営のために、薬剤師数を減らす方向に動くことも予想できます。勤務環境も変化するので、夜勤が必要な病院薬剤師も多くなるでしょう。
病院薬剤師として必要な存在になるためには、専門性を高めたり、コミュニケーション能力をさらに身につけたりするなどの努力が必要になるでしょう。
製薬企業の将来性と求められるスキル
製薬企業は、以前よりも厳しい状況が続くでしょう。というのは、医薬品関係企業の従事者は、2016年には30,265人でしたが、2022年には25,786人まで減少しています。
理由には国の後発医薬品使用促進の方針で、後発品のシェア拡大や新薬が発売されにくくなったこと、薬価改定による影響が大きいことがあげられます。今後、医薬品の市場は厳しくなってくるでしょう。
しかし、製薬企業は調剤薬局や他の職種と比較すると、比較的高収入の傾向があります。そのため、人気の職種です。
特に医薬品の営業を行うMR職になると、営業スキルやコミュニケーション能力、医薬品の薬学・医学をはじめに法律や規制についての知識を身に付けられます。一般的な薬剤師の知識にプラスして、専門領域のスキルを身につければ、将来的に需要の高い人材になれるでしょう。
MR職以外にも、研究開発、臨床開発、安全性情報管理(ファーマコビジランス)といった分野では、高度な専門性を持つ薬剤師の将来性は依然として高いままです。
特にAIを活用した創薬や、膨大な治験・市販後データを解析するスキルは、今後の製薬企業で極めて重要になります。業界の先行きに不安を感じるかもしれませんが、語学力を磨いて国際的な業務に携わるなど、自らの付加価値を高めることで、代替不可能な人材として活躍の道は大きく開けます。
参考:
平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況|薬剤師、令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|薬剤師
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)転職市場から見る薬剤師に求められるスキル

現在の転職市場では、単に調剤経験があるだけでなく、プラスアルファのスキルを持つ薬剤師が強く求められるようになってきています。転職コンサルタントの視点から見ると、特に重要視されるのは「コミュニケーション能力」「専門性」「マネジメントスキル」の3つです。
薬局では、患者や医師と円滑に連携できるかかりつけ薬剤師の経験者が、ドラッグストアでは、調剤もOTC販売もできる柔軟性と接客スキルを持つ人材が人気です。
病院では、チーム医療に貢献できる専門薬剤師が、企業では、特定の分野に特化した知識や語学力を持つ人材が求められる傾向にあります。自身の将来性を高めるためには、AI時代に通用する付加価値を意識したスキルアップが欠かせません。
コミュニケーション能力の重要性
対人業務が中心となる今後の薬剤師にとって、コミュニケーション能力は最も重要なスキルの一つです。
患者に対しては、専門用語を避け、分かりやすい言葉で薬の効果や副作用を説明し、不安を取り除く傾聴力と共感力が必要になってきます。例えば、高齢の患者には、生活スタイルを丁寧にヒアリングし、飲み忘れを防ぐ工夫を一緒に考えるといった対応が大切です。
また、医師に対しては、処方の意図を尊重しつつ、薬学的知見に基づいた的確な疑義照会や代替薬を提案する論理的な対話力が不可欠となります。
専門知識とスキルアップの必要性
薬剤師としての市場価値を高め、将来性を確かなものにするためには、専門知識の継続的なアップデートが不可欠です。
継続的な知識のアップデートの指標となるのが「認定薬剤師」や「専門薬剤師」の資格です。例えば、「がん専門薬剤師」や「在宅療養支援認定薬剤師」などの資格を取得すれば、特定の分野で高度な知識とスキルを持つ証明となり、転職やキャリアアップに有利に働きます。
資格取得は、日々の業務に追われる中で大変な努力が必要ですが、変化の激しい時代を生き抜くための自己投資として、極めて重要と言えるでしょう。
薬剤師にかかわる環境の変化とは?
業務の自動化や機械化といった薬局内の環境、調剤報酬および働き方改革など制度改正による変化は、薬剤師が働くうえでは避けて通れないものです。それに対応して、薬剤師も変わる必要があります。
ここでは、薬剤師にかかわる環境の変化について解説します。
登録販売者の需要増加と薬剤師業務への影響
2021年の規制緩和(通称「2分の1ルール」撤廃)は、地域における安定的な医薬品提供体制の確保と、育児などで離職した登録販売者のキャリア継続支援を背景に行われました。
これにより店舗管理者要件のうち、過去の実務経験のブランクに関する要件が緩和され、登録販売者の活躍の場が広がりました。ドラッグストアなどでは、育児・介護などの理由で長期間離職していた登録販売者でも店舗管理者として復帰しやすくなり、店舗運営の自由度が増しました。
この変化は、薬剤師がOTC医薬品販売のシフトから解放され、本来の専門性が求められる調剤業務や在宅医療、健康サポート業務など、より付加価値の高い仕事に集中できる環境を生み出すというポジティブな影響を与えています。
調剤助手制度の導入と薬剤師業務への影響
調剤助手(ピッキング業務などを担当する無資格のスタッフ)の活用は、薬剤師の業務効率化に大きく貢献します。
薬剤師でなくても行える錠剤のピッキングや在庫管理、ラベル貼りといった対物業務を調剤助手が担うと、薬剤師は監査業務や服薬指導、疑義照会といった専門性が不可欠な業務に専念できます。
これにより、患者と向き合う時間が増え、より質の高い医療サービスを提供できるだけでなく、薬剤師自身の業務負担やストレスの軽減にも繋がります。まさに、対人業務へシフトするための重要な環境整備と言えるでしょう。
6年制薬学教育の施行
2006年度から薬学教育制度が変更になり、薬剤師の修業年限が4年から6年に延長されました。これに伴い、5年時の病院と薬局での約6ヶ月の長期実務自習を履修が義務づけられました。6年制薬学教育では、医療人として相応しい質の高い薬剤師養成を目標にしています。
参加型学習の長期実務実習では、問題解決能力が醸成され、知識や技術に加えて豊かな人間性、コミュニケーション能力などを併せ持つ薬剤師が毎年誕生し、活躍しているのです。
また、6年制薬学教育には、医療の高度化や多様化に対応できる実践能力の養成、生涯にわたる自己研鑽の重要性への理解が期待されています。質の高い薬剤師の継続的な輩出は、国民の健康増進に寄与することが期待されています。
薬剤師の働き方の変化と多様化
厚生労働省発表の令和4年(2022年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況によれば、女性薬剤師の割合は61.6%です。もともと復職しやすいという点で女性に人気があった薬剤師ですが、近年は性別を問わず働き方が大きく変化しています。
男性の育児休暇や社会保険の加入条件拡大など、制度改革が進むことで今までは働くのが難しかった人も働きやすくなるでしょう。企業も職場環境の整備をすることで、優秀な人材の確保が期待できます。
参考:令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況|薬剤師
薬剤師の間で注目されている最新動向

薬剤師業界の最新トレンドとして最も注目されているのが「オンライン服薬指導」の普及です。
2020年の薬機法改正では条件付きで解禁され、新型コロナウイルス禍の特例措置を経て、2022年から定着しました。当初は普及が緩やかでしたが、電子処方箋の導入拡大に伴い、オンライン診療から服薬指導、決済、医薬品の配送までをワンストップで完結できるサービスも登場しています。
今後、患者の利便性向上や薬局の業務効率化の観点から、この流れはさらに加速していくとみられ、薬剤師の将来性を左右する重要な動向です。
ここでは、薬剤師の間で注目されている、新しい動きについて解説します。
かかりつけ・健康サポート業務
今後は在宅医療や地域包括ケアシステムの構築を見据えて、かかりつけ薬局や健康サポート業務の需要が高まっています。かかりつけ薬局と健康サポート薬局が、それぞれどのような役割を果たしているのか、詳しく解説します。
かかりつけ薬局・薬剤師
かかりつけ薬局・薬剤師のメリットとして、以下が挙げられます。
● かかりつけ医をはじめとした医療機関との連携
● 服薬情報を1ヶ所でまとめて管理
かかりつけ薬局では、薬剤師が処方医や地域の医療機関と連携して患者のケアにあたります。ひとりの患者の服薬状況を1ヶ所の薬局でまとめて管理していることから、患者にとって安全に薬を使用できる点がメリットです。
かかりつけ薬剤師になるには、以下の要件を満たす必要があります。
● 当該薬局に週32時間以上勤務、かつ1年以上在籍
● 医療に関する地域活動への参画
● 認定薬剤師の資格取得
健康サポート機能
健康サポート機能の概要は、以下のとおりです。
● 医療機関受診の提案や紹介
● 要指導医薬品や介護用品選びのサポート
● 週末や休日にも営業
● プライバシーに配慮した相談スペース
● 健康相談に関するイベントの開催
かかりつけ薬局の機能と健康サポート機能の両方を備え、厚生労働大臣が定める一定基準を満たすと「健康サポート薬局」となります。
サポート薬局では薬以外にも、未病の来局者から健康全般や介護に関する相談を受けることから、幅広い知識が求められます。
セルフメディケーション
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として健康の維持および疾病予防の取り組みによって、一部医薬品の所得控除が受けられる仕組みです。
対象となるOTC医薬品は1500種類以上で、購入時のレシートや領収書に、対象商品である旨が記入されます。患者がセルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告を行わなくてはなりません。
OTC医薬品は薬局やドラッグストアで処方箋がなくても購入できますが、患者が自分で選択するのは難しいと考えられます。そのため、薬剤師は患者のセルフメディケーションをサポートする必要があります。
オンライン服薬指導の普及と薬剤師の役割変化
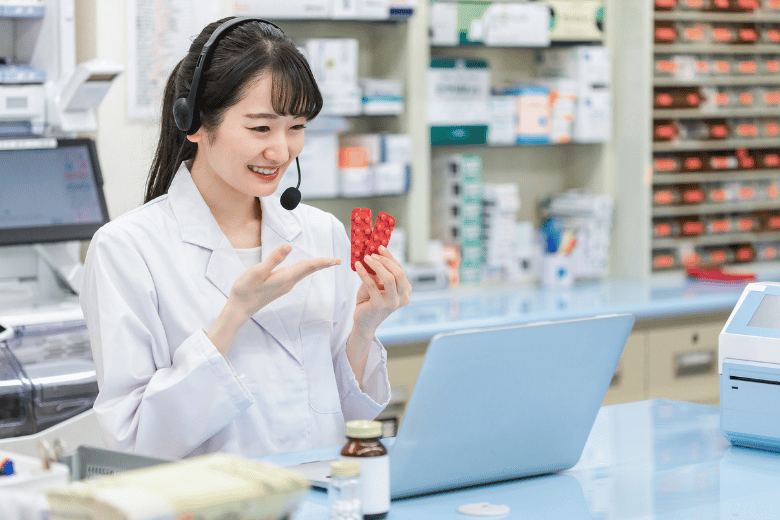
オンライン服薬指導は、コロナ禍における特例措置(0410対応)をきっかけに人々に周知されるようになり、2022年の薬機法改正で定着、薬剤師の新たな働き方としてなじみつつあります。
電子処方箋の普及も後押しとなり、導入する薬局は着実に増加しています。この変化に伴い、薬剤師の役割も進化が求められます。画面越しながらも、患者の状態を的確に把握し、対面と変わらない質の高い指導をするための高度なコミュニケーションスキルが必要です。
また、ICT機器をスムーズに使いこなすリテラシーや、個人情報を適切に扱うためのセキュリティ意識も不可欠となります。オンラインはあくまで手段であり、その先にある薬学的ケアの質こそが将来性を決めます。
オンライン服薬指導のメリットとデメリット
オンライン服薬指導には、患者側・薬剤師側双方にメリットとデメリットがあります。
【オンライン服薬指導のメリットとデメリット】
| メリット | デメリット | |
| 患者側 | ・ 薬局へ行く時間と交通費の節約 ・待合室での待ち時間解消 ・二次感染リスクの解消 | ・通信環境やICT機器が必要 ・対面に比べて細かいニュアンスが伝わりにくい不安がある |
| 薬剤師側 | ・業務効率化が進む ・遠隔地の患者への対応が可能になる | ・患者の状態(顔色や匂いなど)を五感で把握しにくい ・機器のトラブル対応が必要 |
対応しやすく、時間を効率的に使えるようになるのは両者共通です。
今後の展開と薬剤師に求められる対応
将来的に、オンライン服薬指導はさらに進化すると予測されます。電子処方箋の全国的な普及により、オンライン診療から指導、配送までが完全にシームレス化するでしょう。
また、ウェアラブルデバイスなどから得られる個人の健康データを服薬指導に活用するような、先進的な取り組みも期待されます。
このような未来に対応するため、薬剤師はICTスキルを磨き続けると共に、オンライン特有のコミュニケーション手法を習得する必要があります。画面越しでも信頼関係を築き、的確なアセスメントをする能力が、これからの薬剤師の価値を大きく左右するでしょう。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)薬剤師としてキャリア形成する方法5選

AIやIT化で存在も危ぶまれている薬剤師ですが、そのような状況の中で、どうキャリアアップすればいいのでしょうか。ここでは、薬剤師としてキャリア形成する方法5つ紹介します。ほかの方法もいろいろ考えてみましょう。
コミュニケーションスキルを磨いて「かかりつけ薬剤師」を目指す
たとえAIが発達したとしても機械である以上、患者とコミュニケーションを取るのは大変です。患者とコミュニケーションを取りながら服薬指導や相談対応をするのは、これまでどおり薬剤師が担う業務です。
また今後は、かかりつけ薬局や健康サポート業務の需要が高まると予想されています。患者の心情に寄り添いながら、親身にコミュニケーションを取ることができれば、かかりつけ薬剤師として信頼を得られるでしょう。
患者のニーズに応え、選ばれる薬剤師になるためには、コミュニケーションスキルをさらに磨くことが大切です。
かかりつけ薬剤師を目指すにあたり、3年以上の薬局勤務経験や認定薬剤師の取得などの要件があるため、不足している内容がないか確認しておきましょう。
マネジメントスキルを身につけて「管理薬剤師」になる
将来的にキャリアアップを目指すのであれば、マネジメントスキルも必要です。具体的には、薬局各店舗の責任者である「管理薬剤師」が該当します。
管理薬剤師は、薬機法(医薬品医療機器等法)によって、医薬品を取り扱う薬局や店舗に配置が義務付けられています。医薬品の在庫管理や品質管理、薬剤師の教育・監督が管理薬剤師の役割です。
管理薬剤師にキャリアアップするために、必要な試験はありません。勤務している薬局やドラッグストアで、内部昇進する形になります。
また、「管理薬剤師」を募集している企業に転職するのも一つの方法です。地域支援体制加算の要件のため、管理薬剤師は「薬剤師として5年以上の実務経験」が求められています。ただ、経験年数が満たない場合は、管理薬剤師候補として採用に至る場合もあるため、気になる求人があれば問い合わせてみましょう。
現場で経験を積み、スキルを身につけることで管理薬剤師への道が開けていきます。
管理薬剤師については、以下の記事で詳しく解説しています。
管理薬剤師の仕事内容は、一般的な薬剤師とどのように違うのかご存知でしょうか? 管理薬剤師は、薬局などの医薬品関連業種で設置が定められている責任者のことで、薬局の管理や薬局開設者への意見提出といった独自の責務を担っています。 管理[…]
専門性を高めて認定薬剤師資格を取得する
薬剤師として専門性を高めるには、認定薬剤師や専門薬剤師の資格を取得するのも有効です。
認定薬剤師になるためには一定期間、集合研修や自己研修を受け、定められた単位を取得しなければなりません。単位を取得すると、有効期限つきの証明が受けられます。
認定薬剤師になると、最新の知見を有していると見なされ、ほかの薬剤師と差別化を図ることができるでしょう。
認定薬剤師になったあと、さらに各専門領域での研究業績を伸ばすことで「専門薬剤師」に認定されます。専門薬剤師の認定後は、5年ごとに資格更新が必要です。
専門薬剤師には、がん専門薬剤師や感染制御専門薬剤師、精神科専門薬剤師などがあります。通常の薬剤師と比べて確かな専門性や経験を証明できるため、キャリアアップや年収アップが見込めます。
例えば、「がん専門薬剤師」はチーム医療で抗がん剤の専門家として活躍でき、「在宅療養支援認定薬剤師」は高齢化社会で需要の高い在宅医療のスペシャリストとして評価されます。
これらの資格は、専門手当による年収アップに繋がるだけでなく、転職市場においても大きなアピールポイントとなり、キャリアの選択肢を大きく広げることに繋がります。
高齢化社会に備えて、在宅医療の経験を積んでおく
現在、日本では少子高齢化が進んでおり、在宅医療の需要が高まっています。調剤薬局やドラッグストアでも、在宅医療への取り組みが推進されています。
日本薬剤師会が策定した在宅療養推進アクションプランにおいて、薬剤師が地域のチーム医療に参画する際の役割が定められました。
在宅医療を受ける患者の自宅に薬剤を持参し、服用管理や健康相談を行うのが薬剤師の役割です。認知機能や身体的機能が衰えた患者に対しては、薬の保管が適切に行われているかも確認します。
外国語の勉強にチャレンジする
近年日本で暮らす外国人の増加に伴い、語学が堪能である薬剤師の需要が高まっています。この機会に、外国語の勉強にチャレンジするのはいかがでしょうか。
語学力があれば、外国人患者への対応が可能です。また、製薬企業では海外への出張、国際共同治験への参画など、グローバルに活躍できるチャンスが広がります。さらに、海外で開催される学会に参加し、最新の知見も得られます。
語学は新しい可能性を切り開くために重要なツールです。学生時代からの学習が望ましいですが、社会人になってからでも習得する価値は十分にあります。自身のキャリアアップと、医療の国際化に貢献するために、優秀な人材を目指しましょう。
薬剤師のキャリアップ転職は”ヤクジョブ”
転職をお考えの薬剤師の方は、「ヤクジョブ」への登録がおすすめです。
AIの台頭が心配されている薬剤師ですが、ヤクジョブでは専任コーディネーターが丁寧な聞き取りをして、ライフスタイルやキャリアプランに合わせたお仕事をご案内します。非公開求人も含め気になる求人が見つかった後は、給与交渉や面接サポートなども親身に行います。
まずは「ヤクジョブ」へ登録して、キャリアアップの第一歩を踏み出してみるのはいかがでしょうか。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)まとめ
この記事では、薬剤師の職場別将来性、環境の変化、注目されている動向、今後仕事がなくなるかどうかキャリア形成する方法について、解説しました。
今後は人口の減少や薬剤費の抑制にともなって、薬剤師の需要が危惧されている傾向にあります。
一方で、少子高齢化も進むので、これまで以上に薬剤師の存在が必要とされています。薬剤師として確かなキャリアを形成していくためには、専門性を高めたり、マネジメントスキルを身につけたりすることが大切です。
よくある質問
薬剤師の将来性について、多くの方が抱く疑問にQ&A形式で答えます。AIの台頭や薬剤師数の増加など、不安を感じるニュースが多い昨今ですが、正しい情報を知ることで、今後のキャリアプランを描くヒントにしてください。
AIでなくなる仕事ランキングで薬剤師は?
2013年にオックスフォード大学の研究者が発表した論文では、薬剤師の仕事がAIに代替される確率は低いと結論付けられています。
これは、調剤という作業だけでなく、患者とのコミュニケーションや複雑な薬学的判断など、機械には難しい業務が多く含まれるためです。単純作業は代替されても、専門職としての役割はなくならないと考えられています。
今後、薬剤師数はどうなるのでしょうか?
厚生労働省の需給推計によると、将来的には薬剤師の供給数が需要を上回る「飽和状態」になる可能性が示唆されています。しかし、これは全国平均の話であり、都市部と地方では大きな偏在があります。特に地方や中小の薬局・病院では、依然として薬剤師不足が続く見込みです。
今後は、地域や専門性によって需要が大きく異なってくるでしょう。
薬剤師は将来なくなる仕事でしょうか?
なくなりません。ただし、役割は大きく変化するでしょう。AIが定型的な対物業務を担うようになり、薬剤師はより専門的な対人業務、例えば在宅医療やチーム医療における薬の専門家としての役割が中心になります。
変化に対応できる薬剤師には、むしろ活躍の場が広がる将来性があります。
薬剤師は余っていますか?
2024年現在、有効求人倍率は依然として2倍を超えており、全国的に見れば薬剤師は不足気味です。
しかし、都市部では充足感が出始めており、将来的には飽和が懸念されています。かかりつけ機能や専門性など、付加価値を持つ薬剤師とそうでない薬剤師とで、需要の二極化が進むと予想されます。
将来なくならない仕事は何ですか?
一般的に、高度なコミュニケーション能力、複雑な問題解決能力、創造性、ホスピタリティが求められる仕事は、AIに代替されにくいと言われています。薬剤師の対人業務はまさにこれに該当します。
患者の不安に寄り添い、専門知識を基に最適な解決策を提案する仕事は、今後も人間にとって不可欠な役割であり続けるでしょう。


