「薬剤師に話をして何になるんだ」「薬剤師に話す必要はない」などと、患者からクレームを受けた経験はありませんか?薬剤師として働いていれば、一度くらいは誰しも似たようなクレームを受けることでしょう。
今回は、なぜ患者は「薬剤師と話したくない」と感じてしまうのか、原因について解説するとともに、うまく対処するためのコツをご紹介します。日々の業務の参考になれば幸いです。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)薬剤師に対するクレームはどの様なものがある?
薬剤師として働く中で、患者から直接クレームを受けた経験がある方は多いのではないでしょうか。
● 説明がわかりにくい
● 薬代が高い、ほかの薬局と料金が違う
● 説明はいらないから指導料を取らないでほしい
● 薬剤師と話したくない
● 話しても意味がないのでやめてほしい
などのクレームが代表的です。薬剤師に非がないケースもありますが、対応の工夫で改善できるものもあります。とくに、「薬剤師と話したくない、話す意味がない」というクレームは、インターネットで薬の情報を手軽に調べられる時代になったことも影響しているでしょう。
こうした意見を真摯に受け止め、薬剤師側が工夫を凝らし、信頼を得られるようにすることが大切です。
薬剤師と話したくないと思う人がいる理由
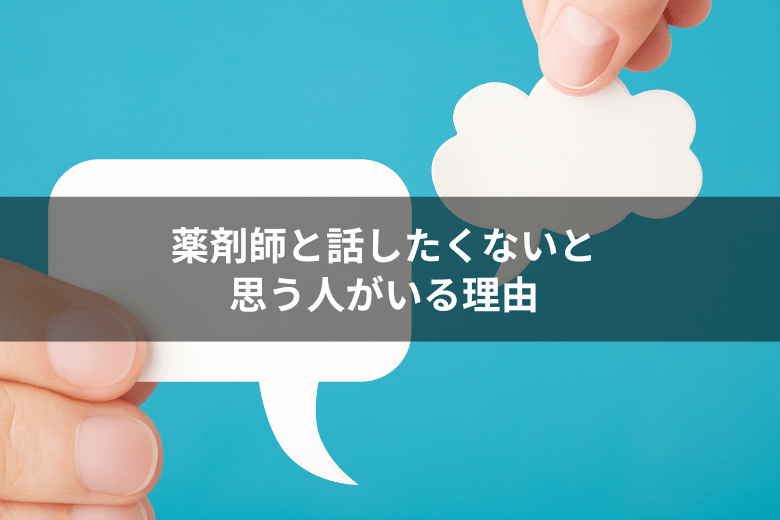
薬剤師と話したくないと感じてしまうのには、患者なりの理由があります。よくある理由を3つ挙げますので、今後の対応に活かしていきましょう。
薬剤師に話す必要性がわからない
患者は、「医師に病状を話した上で薬が出ているのだから、薬剤師に同じ話をする必要がない」と考える方もいます。一般の方には「医薬分業」の意義は浸透していません。
医師から「1日3回飲んでください」など簡単に説明を受けていることも多いため、薬剤師とのやり取りが「二度手間」のように感じてしまうのは、ある意味当然です。薬剤師がなぜ確認をしているのか、理由やメリットを知ってもらう必要があるでしょう。
「調べればわかる」と思われている
現在は、インターネットが広く普及したことで、誰でも薬の情報を簡単に検索できるようになりました。そのため、「わざわざ薬剤師に聞かなくても、気になったら自分で調べれば良い」と考える患者が増えています。
実際、患者も添付文書を見ることができる以上は、「調べても、解釈の難しいこと」「自分の症状・病態に合った内容」など、付加価値のある情報を提供できなければ、薬剤師の存在意義は薄れていってしまうでしょう。
同じ話に飽きている
薬を受け取るたびに同じ説明・同じ質問が繰り返されれば、誰でも「説明はわかっているから、早く渡してほしい」と感じてしまうでしょう。とくに、慢性疾患で長く通院している方は、処方内容も大きくは変わりません。
流れ作業のように全員に同じ質問を繰り返すのではなく、一人ひとりに合った指導内容にアレンジする、前回の会話を踏まえた確認をするなど、薬剤師側の工夫が必要不可欠です。
薬剤師と話したくない方への対応策
医薬分業の重要性やリスクをしっかり説明する
医療従事者にとっては当たり前になっている「医薬分業」ですが、意義をよく知らない患者も少なくありません。
薬剤師が、医師とは異なる視点で処方内容をチェックすることで、処方ミスやよくない飲み合わせを防ぎ、安全性を高められるという点を丁寧に説明し、理解を得る様にしましょう。
薬剤師との会話は形式的なものではなく、安全のためだとわかれば、協力を得られやすくなります。
問診票の記入を断られたら口頭で確認
問診票では、現在治療している病気や服用中の薬、アレルギー、飲酒や喫煙の状況など、プライバシーに関わる情報を伺います。もし記入を断られてしまっても、必要な情報である以上は確認しなければなりません。
「安全にお薬を飲んでいただくために必要なことなので、口頭で確認させてください」などと声かけし、答えてもらえるような雰囲気作りをしましょう。質問は簡潔に、最低限のやり取りにとどめる配慮も必要です。
指導内容の質を上げ信頼関係を築く
薬剤師と話したくないと感じる要因には、薬剤師側の対応に原因がある場合も少なくありません。形式的な説明に終始するのではなく、「聞いてよかった」と感じられる説明・指導ができるように、スキルを磨き、信頼関係の構築を目指しましょう。
患者の状況に応じた具体的なアドバイスや、日常生活への応用例などを盛り込むと、より価値を感じてもらいやすくなります。結果として、信頼関係の構築にもつながります。
会話の内容が聞こえないようにプライバシーに配慮する
感染症やがんなど、あまり周囲の方に聞かれたくない病状の方は多くいます。個室の用意が難しくとも、できる工夫はいくつもあります。
● 声のトーンを抑える
● 待合スペースと投薬窓口の向きを変える、距離をとる
● 薬情を指し示しながら「この薬」と話すなど、病名や薬剤名を出さない
プライバシーに関する不安を和らげられるように、こういった工夫を取り入れてみましょう。問診票に「話すときは人に聞かれないようにしてほしい」とチェックする項目を設けるのも、良いのではないでしょうか。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)薬剤師と話したくない方に話してもらう工夫とポイント
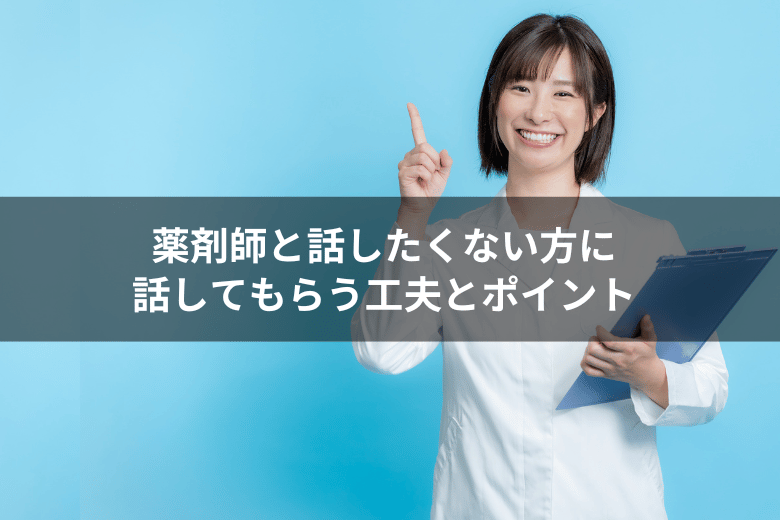
質問している理由を説明する
なぜ質問をしているのか、なぜ情報を教えてほしいのかについて説明すると、患者からも納得が得られやすくなります。
たとえば、眠気の出る薬を使う方に対して危険作業の有無を聞きたい場合、「お仕事は何をしていますか」と尋ねることがあると思います。唐突に聞かれると、「薬と仕事に何の関係があるのだろう」と不審に思われるかもしれません。「眠気が出やすい薬なので、安全のため、生活についてお伺いしています」のように、まずは理由を明確に説明してみましょう。
Yes/Noで端的に答えられる質問にする
長く会話をするのが苦手な方、体調がすぐれない方でも、Yes/Noで簡単に答えられる質問であれば負担が少なく、答えやすくなります。
「この薬は、以前にも飲んだことがありますか?」「吐き気や下痢の症状はありますか?」など、質問の仕方を工夫し、簡潔にやりとりできるようにしましょう。
短いやり取りでも、必要な情報収集や説明ができれば、問題ありません。
薬剤師にできることを明確にする
薬剤師として、患者の服薬管理にどのように貢献できるか、何を伝えられるかなどをアピールすることも大切です。
あまり医療機関にかかる習慣がなければ、「薬局は医者の処方通りに薬を集めるだけの場所」のように思っている方もいます。一包化、剤形変更、用法や錠数の整理など、薬剤師が一人ひとりに合わせて患者や医師へ提案できることはいくつもあります。
薬剤師の業務について説明するチラシを掲示するなど、理解を得るためのアピールをしてはいかがでしょうか。
新しい情報を提供できるよう記録を活用する
「誰にでも同じ質問、同じ説明」では、「自分でインターネットで調べればわかる」と思われても仕方がありません。一人ひとりの年齢や既往、過去の服用歴、生活状況などに合わせた指導をおこなって初めて、患者個人にとって有益な服薬指導になります。
また、患者自身が知りたい情報を得ることができれば、「薬剤師は自分のことを理解してくれている、信頼できる」という認識を持ってもらうことにもつながります。患者についての情報や指導した内容などはしっかり記録をとり、次の指導に役立てましょう。
会話が続かない際の対処法
相手の話を聞きたいという姿勢を見せる
患者さんが話しにくそうにしている時、話したくないという態度を示している時こそ、薬剤師側の聞く姿勢が問われます。無理に言葉を引き出そうとせず、患者の沈黙や戸惑いを受け入れる態度が、安心感を与える第一歩になるのではないでしょうか。
相槌や目線を合わせるといった傾聴の態度を示した上で、質問を投げかけたあとに少し待つ、相手のペースで会話する、など、患者の気持ちを尊重することが大切です。
「しっかり聞いてくれた」「気持ちに配慮してくれた」という経験が、「薬剤師に話を聞いてもらおうかな」と考えるきっかけにもつながり、信頼構築への近道となります。
会話の長さにこだわらない
会話の長さは、じつはそれほど重要ではありません。最も大切なのは会話の長さではなく、「患者にとって必要な情報が伝わったかどうか」です。「丁寧に寄り添った指導をしたい」という気持ちは間違っていませんが、会話の長さと内容の質は必ずしも比例しないということを、理解しておきましょう。
要点をおさえて情報を収集し、必要な説明ができていれば、数分の服薬指導でも信頼や安心を与えることは可能です。
無理に会話を引き伸ばさず、患者の状態や性格、ニーズに合わせて柔軟に対応することが、質の高い服薬指導につながります。
薬剤師に対するクレームと対応の実例
薬剤師に教える必要はない!と怒る患者
アレルギー膠原病科から、メトトレキサートが新しく処方された患者に対し、「今日はどういった症状で受診されましたか」と聞いたところ、「病院でさんざん話したのに、薬剤師にまで同じ話をする必要はないだろう!一刻も早く帰りたいから、早く薬を渡してくれ!」と怒らせてしまいました。
「お疲れのところすみませんが、この薬はいろいろな病気に対して使うものなんです。病名によってご説明の内容も変わるので、症状や病名をお伺いしました。」と理由をお伝えしたところ、冷静になっていただくことができました。
病態と合わせて薬の効果について説明したところ、「受診で疲れていて、カッとなって悪かったね。説明でよくわかりました。」と、薬剤師と話をする意義を感じていただけたようです。
何のために質問しているのか、理解を得られるようにしましょう。
何も答えようとしない患者
抗真菌薬の軟膏が処方された患者が来院しましたが、塗布部位の記載がありませんでした。そこで、患者に「今日はどうされましたか」「どの部位に塗るか、説明はありましたか」と聞いたのですが、全く反応してもらえません。
そこで、体のイラストを提示して「どこに塗ると言われていますか?」と聞いてみたところ、指差しで陰部を示してくれました。
糖尿病でSGLT2阻害薬を服用していた方だったため、お薬手帳を指しながら「この薬の影響で今回のような症状が出る場合もあるので、蒸れないように気をつけたり、清潔に保ったりするようにしてください」と指導したところ、「知りませんでした。気をつけます」と興味を持って会話してもらうことができました。
デリケートな話題の場合は、病名などを出さず、聞かれても問題ないような話し方をしてみると良いかもしれません。
薬剤師転職エージェントなら「ヤクジョブ」
患者からのクレームで心が折れてしまった、心機一転新しい環境で働きたいなど、転職をご検討中の薬剤師の方は、薬剤師専門の転職エージェント「ヤクジョブ」に任せてみませんか?
ヤクジョブでは、薬剤師専門の専任コーディネーターが、多数の求人情報の中からあなたのご要望に沿ったものを厳選して紹介します。キャリアや福利厚生だけでなく、職場の雰囲気などの募集要項だけでは分からない部分も考慮してサポートすることが可能です。
転職希望時期がまだ明確でない方や迷っている方も、まずはお話だけでかまいません。お気軽にご相談ください。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)まとめ
今回は、「薬剤師と話をしたくない」「話をする必要はない」と主張する患者の気持ちや、対応する際のコツについて解説しました。
薬剤師をしていれば、一度や二度は薬剤師に対して好意的でない患者に出会います。必ずしも患者側に問題があるわけではなく、薬剤師の態度やスキルを見直すことが解決につながる場合も多いです。誰にでも同じ質問をするのではなく一人ひとりの状態に合わせる、薬剤師の業務について理解が得られるよう説明するなど、薬剤師にできる工夫はいくつもあります。
今回の記事を参考に、「話してよかった」と感じてもらえるような薬剤師を目指してみてください。

