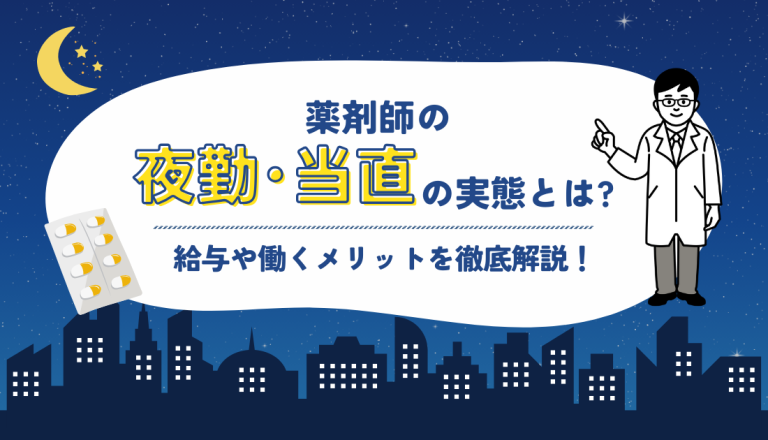急性期病院を中心に、薬剤師も夜間勤務をしている施設はあります。「病院薬剤師に興味があるけど、夜勤って実際どんなことをやるのだろうか」など、実態がよくわからずに一歩を踏み出せない方もいるのではないでしょうか。
今回は、夜勤・当直など夜間勤務で何をしているのか、給与はどうなっているのかなど、夜勤の実情についてお伝えします。後悔しない職場選びをするため、参考にしてください。
\あなたに合った職場をお探しします!/
薬剤師の夜勤・当直とは?仕事内容と実態を解説

医師や看護師の夜勤はなんとなくイメージがついても、薬剤師の「夜勤・当直」は何をするのかわからないという方もいるでしょう。まずは、夜勤・当直の定義や、どのような業務をするかについてご紹介します。
病院の場合
夜勤や当直などの夜間業務があるのは、急性期病院が中心です。薬剤師が夜間も院内に常駐し、救急外来の来院患者や、緊急入院患者などの処方に対応します。
夜勤は、夕方頃から出勤し、翌朝まで働くスタイルのことです。夜勤の勤務時間は、法定労働時間である週40時間に含まれます。
たとえば、16時〜翌9時(休憩1時間、16時間勤務)であれば、2日分の勤務として扱われるのが一般的です。施設によって、夜勤者が定期処方を調剤するなど業務内容が定められており、通常勤務と同様に業務をおこないます。
一方、当直は時間外勤務の扱いであり、日中の勤務から引き続き夜間に泊まる勤務です。労働基準法で「原則的に状態としてはほとんど労働する必要がない」業務とされており、夜間にどうしても必要になった薬の対応などをおこないます。
夜勤・当直の違いを知っておかなければ、「想像と違って、勤務がきつい」ということになりかねません。どちらの体制をとっているか、また、実際の業務量はどの程度か等、事前に確認しておきましょう。
調剤薬局の場合
夜勤(当直)とは異なりますが、調剤薬局は夜間も患者対応をおこなう「24時間対応」の体制を整えているところも増えています。営業時間外に患者からの連絡を受けて、質問対応や、調剤・お薬のお渡しをおこないます。
夜間・休日対応は、薬局内で交代しながら担当していることが多く、厚生労働省の調査によると27%の薬剤師が週に1回以上携わっているそうです。
近隣の薬局と連携し、夜間・休日対応の担当になる頻度を減らすよう輪番体制をとっているところもあります。
夜勤がない職場もある
薬剤師として働く中では、夜勤(当直)のない職場も多いです。慢性期病院のほとんどは夜勤(当直)がありません。24時間営業ではないドラッグストアや24時間対応をしていない調剤薬局、製薬会社なども、夜間の勤務はありません。
プライベートを大切にしたい、子どもが小さいので夜間勤務は避けたい、体力的に自信がないといった方でも、安心して働ける職場はあります。自分に合う条件で探すようにしましょう。
夜勤薬剤師の給与はいくら?手当や収入の詳細

「夜勤は給与が高い」というイメージをお持ちの方は多いでしょう。実際どの程度変わるのか、例を挙げてご紹介します。
労働基準法により、深夜帯(22時〜翌5時)に勤務をした場合には25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。そのため、22時〜翌5時の7時間に勤務をすると、日中に同じ時間働くよりも給与が高くなるのです。
たとえば、時給2,000円で7時間働く場合を考えてみましょう。
| 日勤帯 | 2,000円×7時間=14,000円 | |
| 夜間帯 | (2,000円×1.25)×7時間=17,500円 | 差額:3,500円 |
日勤帯に比べて、夜勤帯では3,500円の増額となります。
また、それとは別に「夜勤手当」「夜間調剤手当」などの名称で手当がつく施設も多いです。
施設によりますが、数千円〜1万円程度の手当が期待できます。そのため、1回の夜勤で1万円前後の収入増につながると言えます。
夜勤のある職場に就職を考える場合は、夜勤の回数や手当の額を確認しておくと、給与の予測もつけやすいです。
\あなたに合った職場をお探しします!/
薬剤師が夜勤で働くメリットはある?
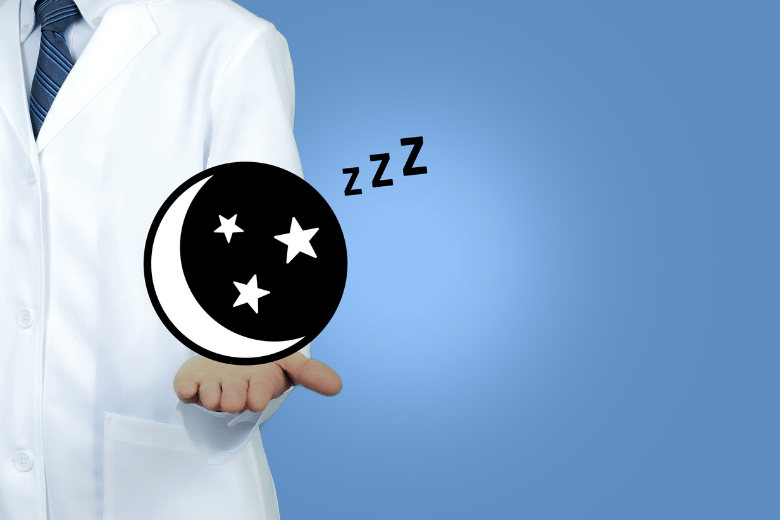
夜勤をすることで、どのようなメリットが得られるでしょうか?今回は、次の3点のメリットについて解説します。
● 平日に時間ができる
● 人間関係のストレスが少ない
● スキルアップやキャリアアップにつながる
給与が上がる
先ほどご紹介したように、22時から翌朝5時までは賃金が25%増しになるため、月に何度か夜勤をおこなえばかなりの給与アップになります。
高い給与を得ることを優先的に考えるのであれば、基本給や昇給率のほか、夜勤の有無や回数、手当の額についても着目すると良いでしょう。
夜勤の回数は施設によりますが、一般的に、薬剤師の人数が少ない施設では月当たりの夜勤回数は多くなります。
稀ですが、夜勤のみをおこなう「夜勤専従」という働き方もあります。労働基準法に従うと、週に2回程度、月に10回程度まで夜勤をすることができ、日中の休みを確保しつつ給与も維持できる点がメリットです。
平日に時間ができる
夜勤の翌日(いわゆる夜勤明け)は休みのため、有給休暇を取らずに用事をこなすことが可能です。
たとえば、月曜から火曜にかけての夜勤だった場合、火曜日に銀行や役所、医療機関の受診、レジャーなど、平日にしかこなせない用事を入れることで、有給休暇を温存することができます。
夜勤の翌日は、十分な睡眠が取れていないことも多いため、もちろん純粋な休日とは異なりますが、時間を有効に使える可能性があるのはメリットです。
また、夜勤の前後で、まとまった勉強時間を確保できるという点もメリットになり得ます。認定・専門薬剤師を目指している方などは、試験に向けて症例を記載したり、集中的に勉強したりするための時間が必要です。
夜勤の前後を活用することで、休暇を取らずに時間を確保できます。
人間関係のストレスが少ない
夜勤は、施設の規模にもよりますが、1人〜2人でこなすことが多いです。薬剤師同士の上下関係などに煩わされることが日中よりも少なくなるため、「夜勤は自分のペースでできて快適」と感じる方もいます。
また、他部署とのやりとりも多くはありません。医師・看護師などから問い合わせの連絡が来ることもありますが、緊急の用事に限られることが多く、クレームなどの対応は日中よりも少ない傾向にあります。
患者対応も最低限になるため、複雑な服薬指導はないケースがほとんどです。
スキルアップやキャリアアップにつながる
前述のとおり、夜勤は1人~2人と少人数で対応することが多く、緊張感がありプレッシャーに感じてしまうこともあるかもしれません。
急性期病院の場合は、救急で来院する患者も多くいます。緊急のなか優先順位を見極めて判断し、適切な薬物治療の提案をする必要があります。また、入院患者の容態が急変した場合には、医師に指示をもとに迅速な対応が求められるなど、気を抜けない状況が続く環境です。
しかし、そんな環境だからこそ、知識や判断力のみならず、医師や看護師などの他職種とのコミュニケーション力、柔軟性を身に着けられます。
薬剤師の夜勤は大変な場面も多いですが、薬剤師としてのスキルを磨け、キャリアアップにつながるチャンスとなるでしょう。
薬剤師が夜勤で働くことにはデメリットも

メリットもありますが、夜勤をすることによるデメリットもあります。ご自身にとって、メリット・デメリットのどちらが大きいか、よく考えておくことが大切です。
● 精神的な負担になる
● 家族と生活時間帯が合わない
生活リズムが乱れる
日中の勤務と夜勤と両方がある場合、どうしても生活リズムは乱れてしまうため、疲労が残りやすくなる、体調を崩してしまうなどのリスクが考えられます。体力に自信のない方・持病のある方などにとっては、夜勤は不安要素となるでしょう。
また、生活リズムが乱れることで、睡眠障害、肥満、生活習慣病などのリスクも、日中にのみ働いている人と比較すると、増加すると報告されています。
夜勤をする場合、より一層健康を意識した生活をする必要がありそうです。
精神的な負担になる
夜間は、入院患者の急変や救急外来の対応など、日頃あまり接することのない病態の患者も多くなります。医師や看護師からの問い合わせも、日中の勤務では馴染みのない内容であることが少なくありません。
「妊婦に使える抗菌薬は何か」など健康被害に直結しうるような問い合わせがあった場合、自分の責任で返答をしなければならない点がプレッシャーに感じてしまうこともあるでしょう。
家族と生活時間帯が合わない
同居家族がいる場合、「夜勤明けで疲れているから昼から寝たい」「夜も早く寝たい」と思っていても、うまくいかない場合もあり、体に負担がかかってしまう可能性があります。とくに、小さなお子さんがいる場合や、高齢の家族がいる場合には、夜勤翌日も自宅でなかなかゆっくり過ごせないかもしれません。
また、夜勤や当直が頻繁にある職場では、家族との予定が立てにくくなってしまう可能性もあります。
\あなたに合った職場をお探しします!/
まとめ
今回は、薬剤師がおこなう夜勤・当直について、業務内容や給与事情、メリット・デメリットをご紹介しました。夜勤をおこなえば給与が増えるなどのメリットもありますが、生活リズムが乱れるのが苦手な方にとってはデメリットもあります。
転職をするにあたり、夜間勤務の有無は大きなポイントです。ご自身にとってどのような働き方がベストなのか、よくイメージしてみましょう。