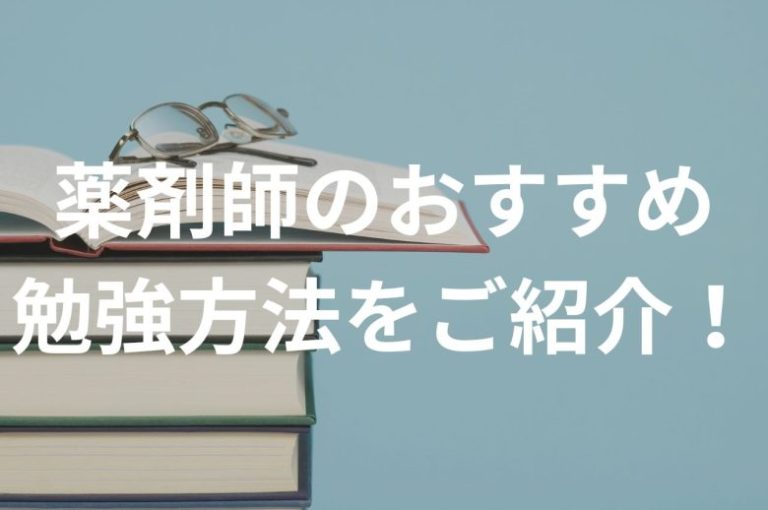薬剤師には生涯学習が必要とわかっているものの、日々の業務に追われて、理想とするスキルアップを実現できていないと感じることはありませんか?
「何から始めたらいいのかわからない」「時間がないから効率よく勉強したい」など悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、おすすめの勉強方法や勉強時間を確保する方法、そして勉強を長続きするコツなどをご紹介します。ぜひ自分に合った学び方を見つけて、なりたい薬剤師像に向けた一歩を踏み出してみてください。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)薬剤師は勉強する必要があるのか?
6年間(あるいは4年間)の大学生活を経て、国家試験をクリアし薬剤師になったからといって、そこで勉強を終わりにすることはできません。
医療は常に進歩を続けており、新しい医薬品や治療技術が開発され続けています。2024年度だけで106もの新薬が厚生労働大臣によって承認されており、それらを把握するだけでも相応の労力が必要です。
薬剤師として適切な服薬指導や疑義照会をおこなうためには、最新の情報を常に追い求め勉強を続けることや、ガイドライン等から即座に調べる力をつけることが必要になります。
一朝一夕では、薬剤師として十分な知識は身につきませんので、日々学び続けなければなりません。
適切な学習方法で、患者の適切な薬物療法に寄与できる薬剤師になりましょう。
薬剤師におすすめの勉強方法7選

薬剤師として働きながら学習を続けるために、おすすめの方法を7つご紹介します。ご自身の生活の中で取り入れられる方法を見つけてください。
セミナー・講習会に参加する
さまざまな薬剤師会や学会、企業などが開催するセミナー・講習会へ参加してみましょう。対面形式のセミナー・講習会だけでなく、オンラインで参加できるものも増えています。
あらゆるテーマのセミナーが全国でおこなわれていますので、興味のあるものを探してみましょう。地域の薬剤師会などが開催するセミナーであれば、同じ地域の薬剤師と交流を持つこともできますので、モチベーションの向上にも繋がります。
Webサイト・アプリで勉強する
近年は、薬剤師向けの記事が掲載されるWebサイトやアプリも増えてきました。話題になっているテーマや、新薬についての情報など、時事的な問題について情報を得やすいのがメリットです。
毎日のように新しい情報が更新されるため、飽きずに情報収集を続けることができます。
通勤時間や昼休み、寝る前の時間など、短時間で勉強するには最適な方法といえるでしょう。
薬局・病院で開催される勉強会に参加する
薬局や病院では、定期的に勉強会が開催されていることも多いです。外部から参加できるものもありますので、探してみてはいかがでしょうか。その職場の業務で求められる内容の勉強会であることがほとんどですので、業務に直結する情報が学べます。
近隣の医療機関の薬剤師と意見交換をする機会も得られるかもしれません。薬薬連携のためにも役立つでしょう。
参考書で勉強する
初学者向けから専門的なものまで、さまざまなテーマで参考書が販売されていますので、自分に合ったレベルでの学習が可能です。
疾患や薬についてだけでなく、薬歴の書き方や服薬指導の方法、新人教育についてなど、何か実務で困っていることの解決につながるものが必ず見つかります。
書店へ行き、役立ちそうな参考書を探してみてはいかがでしょうか?
診療ガイドラインで勉強する
基本的には、医師も診療ガイドラインに則った治療をしています。ガイドラインの内容を知っておけば、医師の処方意図や、薬剤の変更理由などを推察しやすくなるでしょう。逆に、ガイドラインから逸脱した治療にも気がつくことができます。
高血圧、糖尿病など基本的な疾患のガイドラインは把握しておき、改訂されたらポイントだけでもおさえておきましょう。
適切な薬物療法に貢献するために、最も基本的な勉強方法です。
社内の人と情報交換する
薬剤師は、各々が興味に沿って勉強しています。社内の薬剤師と、勉強した内容について情報交換すると、効率よく知識を増やすことができるでしょう。
同じ社内の薬剤師であれば、似たような業務に携わっているため、お互いに有益な情報をやり取りできる可能性が高いです。
また、誰かと一緒におこなうことで、勉強を続けるモチベーションにも繋がります。
学んだことをノートにまとめて見返す
これまでに挙げたような方法で学んだことを、ノート・アプリなどにまとめておきましょう。学んだことを全て覚えておくのは難しいですが、情報を集約しておけば、必要な時にすぐに情報へアクセスすることができます。まとめておけば、復習しようと思ったときすぐに取り組めるため、便利です。
勉強会に参加した場合、資料にメモをすることも多いでしょう。資料やメモの内容も含めて、まとめておくことをおすすめします。
勉強時間が取れない!そんな方へのおすすめ勉強テクニック
忙しくて勉強時間がないから、とスキルアップを怠っていては、求められる薬剤師にはなれません。ちょっとした時間でも続けられる勉強法をご紹介します。
日々のちょっとした疑問を解消していく
業務をする中で、「なぜこの組み合わせで使っているのだろう」「どんな指導をしたらいいのだろう」と、知識不足を感じる場面は、誰にでもあるはずです。
そういった疑問を書き留めておき、1つ1つ解消していけば、かなりの勉強量になります。実務に直結するため、やる気になりやすい方法です。「わからないけど、まぁいいや」と現状維持に甘んじることなく、日々の業務を通じてスキルアップしましょう。
eラーニングを受講する
さまざまな機関が、eラーニングシステムを用意しています。短時間の動画を揃えている機関もありますので、昼休みなどの隙間時間を活用して知識を増やしていくことが可能です。eラーニングを受講して単位を集めれば、資格も取得できます。
日本病院薬剤師会、日本薬剤師研修センター、MPラーニングなど、ご自身が取得したい資格に合ったeラーニングシステムを選び、活用してみましょう。
基本的な書籍をいくつか購入する
毎月何冊も書籍を購入する必要はありませんが、基本となるような書籍は購入し、勉強しておくのが良いでしょう。たとえば、毎年1月に発売される「Evidence Update」シリーズは、高血圧や糖尿病、リウマチ、がん治療などあらゆる分野についての新しい情報がまとまっており、総合的な勉強をするには最適です。
そのほか、興味のある分野、診療科などについて、ご自身のレベルに合ったテキストを購入し、昼休み・就寝前などの時間を見つけて勉強してください。
薬剤師向けの雑誌を読む
薬剤師向けの月刊誌を購読している施設も多いのではないでしょうか?毎月さまざまなテーマについて特集されていますので、1年間読み続ければ幅広い知識を身につけることができます。
昼休みを活用したり、同じ職場の薬剤師と意見交換しながら読んだりすることで、習慣にしやすい勉強方法です。初学者から中堅薬剤師まで、有意義なテーマが設定されていますので、雑誌を手に取ってみてください。
誰かと一緒に勉強する
一緒に勉強する仲間を作っておくと、学習効果が高まるほか、モチベーションの維持にも役立ちます。きちんと学習を続けているかお互いに進捗を確認し合えば、三日坊主を防げるでしょう。学習した内容をシェアするためにアウトプットをおこなえば、知識の定着も見込めます。
身近に仲間を見つけられない方は、SNSの活用もおすすめです。
メーリングリストやアプリに登録
能動的に学習を進められない…という方は、医療従事者向けのニュースアプリなどに登録し、受け取った情報は読むという受動的な学習から始めてみてはいかがでしょうか。「日経DIオンライン」や「MEDICAL TRIBUNE」など、自分に合いそうなものを探してみてください。
毎日情報が送られてきますので、軽く目を通すだけでさまざまな医療情報を得ることができます。得た情報の中で、興味が湧いてきた分野に関しては、ここまでにご紹介したような方法でさらに勉強を深めていきましょう。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)忙しくしても勉強時間を確保する方法3選

忙しい社会人が勉強の時間を確保するには、時間を決めて取り組むことが大切です。習慣化できれば、三日坊主で勉強をやめることなく、毎日続けることができます。
通勤中に勉強する
電車通勤などで、動画を見たり本を読んだりする時間を確保できる方は、その時間を活用して勉強に充ててみましょう。少しずつでも、毎日積み上げれば十分な学習時間を確保できます。
生活の中では、なかなかeラーニングの動画を見る時間を確保できないという方も、通勤時間であれば他の用事に遮られることなく集中できるため、ぜひ時間を有効活用してください。
就寝前の30分で勉強する
就寝前は、SNSを長時間眺める、テレビを流しているなど、無駄な時間を過ごしていませんか?就寝前の学習は、記憶の定着に優れていますので、これまで学習したことの復習や、暗記したい内容の勉強がおすすめです。
業務中に生じた疑問をその日のうちに解決するために、就寝前の時間を使うというのも良いでしょう。1日の終わりをダラダラと過ごさず、有意義に活用してはいかがでしょうか。
休みの日にまとめて勉強する
勤務日には勉強をする余裕がない!という方は、休日に勉強時間をとってみてはいかがでしょうか?
「時間が余ったら勉強する」のではなく、「日曜の午前中は勉強に充てる」のように自分でルールを決めておくのが良いでしょう。
しっかりと時間を確保して勉強できるため、表面的な知識をつけるだけでなく、深く学習することにも繋がります。
勉強を長続きさせるためのコツ5選
勉強を習慣化するのは、簡単なことではありません。勉強を長続きさせるためのコツを5つご紹介しますので、取り入れてみてください。
目標を常に見えるところにおく
勉強に挫折してしまわないよう、「認定薬剤師の資格をとる」「年末までにeラーニングで20単位集める」などの目標をカレンダーや手帳などに記載し、目に入るようにしておきましょう。
また、勉強をしたらカレンダーに◯をつけるなどして、継続できていることを可視化するのも効果的です。特に、達成まで時間がかかるような目標の場合は、中弛みしてしまう可能性もあります。目標を常に掲示しておけば、気持ちを引き締めることができます。
あらかじめ勉強時間を確保しておく
「余った時間で勉強をする」のでは、勉強を続けるどころか、始めることもできないケースが多いです。「勉強のための時間」を、あらかじめ確保しましょう。
朝型生活に変えて出勤前に時間を確保する、設定した学習時間になったらアラームを鳴らすなど、計画的に時間を取れるように工夫してみてください。「昼休みは勉強することにした」と周囲に宣言するのもおすすめです。「朝食を食べたらアプリの情報を読む」「お風呂に入ったらテキストを読む」のように、1日の中で必ずおこなう行動とセットにすると、習慣化しやすくなります。
ご褒美タイムを用意する
一定の目標を達成したら、自分にご褒美タイムを作るのもおすすめです。「2週間、毎日勉強を続けられたら、映画を見にいく」「1か月続けられたら、友人と出かける」など、1週間・1か月と段階的に楽しみを設定することで、モチベーション維持に繋がります。
ただしあまり簡単すぎる目標でも、達成困難な目標でも、モチベーションの維持には逆効果になるので注意してください。趣味の時間やリフレッシュの時間もうまく取りながら、目標達成を目指しましょう。
なりたい姿を定期的にイメージする
何のために勉強をしているのか、目的を見失わないことも、勉強のモチベーション維持に役立ちます。「患者さんから頼りにされる薬剤師になりたい」「専門資格をとって、より良い提案をできる薬剤師になりたい」「チーム医療で、臆することなく意見を言いたい」など、勉強をしてどんな薬剤師になりたいのかをイメージしましょう。
勉強をしている本来の目的を思い出すことで、気持ちを新たにすることができます。
集中できる場所で取り組む
勉強をするには、周囲の環境を整理することも大切です。たとえば、机の上に勉強と無関係なものが置いてあれば、つい手を伸ばしたくなってしまいます。勉強をする前には、机の上を片付け、スマートフォンも遠ざけておくのがベストです。自宅に限らず、図書館やコワーキングスペース、職場の自席などでも勉強はできます。自分が集中できる場所を見つけ、効率よく学習しましょう。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)まとめ
薬剤師として、自分の価値を高めるためには、勉強を続け、知識をアップデートしなければなりません。楽しいことではないかもしれませんが、日々の積み重ねが着実な成長に繋がります。
短時間でも良いので、勉強のための時間を確保することが大切です。
自宅でのeラーニング受講、外部の勉強会への参加、テキストで自己学習など、さまざまなスタイルがあります。自分に合った無理のない学習方法を見つけ、薬剤師として成長していきましょう。