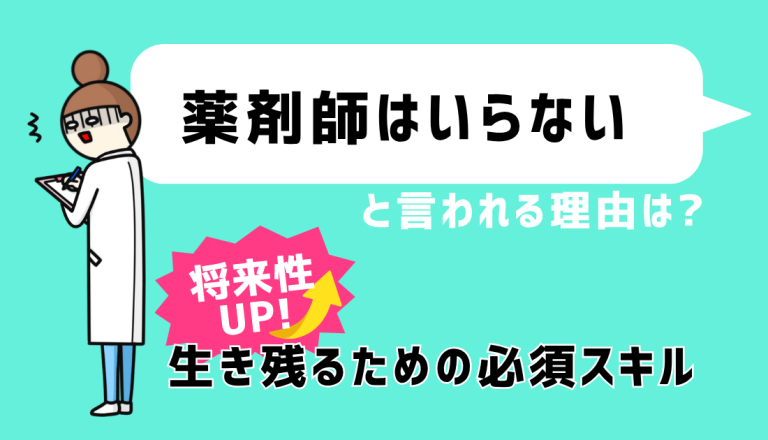「薬剤師はいらない」「将来的になくなる仕事だ」という主張を耳にしたことがあるでしょうか?このような意見が出てしまうのには、さまざまな理由があると考えられます。
どのような理由があれ、時代のニーズに従って自己研鑽を続けていけば、必要とされる薬剤師になれる可能性はあります。今回は、これから必要とされる薬剤師になるためのポイントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
\あなたに合った職場をお探しします!/
薬剤師はいらないといわれてしまう理由とは?

薬剤師は、なぜ「いらない」と言われてしまうのでしょうか?まずは、その理由を把握しておく必要があります。
①業務が見えにくい
薬剤師がいらないと思われてしまう理由の1つとして、一般の方には、薬剤師がどのような業務をしているのか、どのように患者の健康に貢献しているのかが分かりにくいことが挙げられるでしょう。
薬剤師は、処方箋を受け取ってから、相互作用や腎機能による用量調節が不要かなどを考え、必要に応じて医師へ疑義照会をおこなってから、調剤・鑑査・お薬のお渡しをしています。
薬剤師としての知識を活用してチェックをしてはいますが、疑義照会を要しないことも多いです。
そのため、「処方箋を受け取って、その通りに集めて渡しているだけ」のような印象を持たれてしまいやすいのかもしれません。
②対物業務の自動化と非薬剤師への業務移管
2019年4月2日に厚生労働省から発出された「調剤業務のあり方について」は、薬剤師の働き方に大きな影響を与えました。この通達により、薬剤師の指示であれば、薬剤師以外のスタッフでも一部の業務を実施できるようになったのです。
具体的には、処方箋に記載された医薬品を棚から取り揃える行為(ピッキング)や、一包化した薬剤の数量を薬剤師の監査前に確認する行為などが該当します。
ただし、これらの業務は、薬剤師の目が行き届く範囲で実施され、判断の余地が少ない機械的な作業に限られます。軟膏剤の混合や散剤の計量といった、専門的な判断を要する行為は引き続き薬剤師にしか認められていません。
通知による規制緩和は、錠剤・散剤の自動分包機といった調剤ロボットの活用とあわせて、対物業務の効率化を促進するものです。これにより、薬剤師が対物業務に費やす時間を減らし、服薬指導などの対人業務へより注力することが期待されています。
参照:厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長|調剤業務のあり方について
③AIなどデジタル技術の進歩
薬剤師の知識を活かした業務として、相互作用のチェックなどの「処方監査」があります。しかし、AIなどデジタル技術の進歩によって、「薬剤師による処方監査は不要」「AIの方が正確で見落としがない」と考える方も多いです。
そのほか、在庫管理や薬歴管理にも、AIの技術が使われるようになってきています。また、自動調剤ロボットなどデジタル技術の高性能化も目覚ましい発展を遂げています。
今では処方箋のデータを入力するだけで、医薬品の選択から、秤量、配分、分割、分包までをおこなえるようになりました。人間よりもAIの方がミスなくできて安心だという思いが、薬剤師はいらないという主張に繋がっているのでしょう。
過去の膨大なデータを基に処方をチェックするAIや、24時間稼働できる調剤ロボットは、ヒューマンエラーの削減や業務効率化に大きく役立ちます。技術がさらに発展すれば、従来の薬剤師業務の一部が代替される可能性は否定できません。
④「医薬分業」の意義が理解されにくい
日本で本格的に医薬分業が始まったのは、1974年です。処方をする医師と、調剤をする薬剤師とが、お互いの専門性を発揮してより安全な医療を提供するために、医薬分業が始まりました。
ですが、患者の視点から考えると、意義が分かりにくいというのが現状です。「クリニックでそのまま薬がもらえた方が便利で時間もかからない」「医師に症状を説明したのに、また薬局で説明するのが無駄」というように、医薬分業に否定的な気持ちから、薬剤師がいらないという結論になっている可能性があります。
また、日本の医薬分業では、病院で診察を受けた後、薬局で薬を受け取る際に、調剤料や薬学管理料などが別途加算されます。患者にとっては、支払いが増えるというデメリットが目につきやすい一方で、「複数の医療機関からの薬を一元管理し、相互作用や重複投薬を防ぐ」という医薬分業本来のメリットが十分に伝わっていないのが現状です。
そのため、「なぜ病院で直接薬をもらえないのか」という不満が、「薬局や薬剤師はいらない」という意見につながることがあります。
⑤薬剤師の人数は飽和し需要が変化している
薬剤師の数は年々増加しており、2022年には約32.3万人に達しました。一方で、医師・歯科医師・獣医師・薬剤師の有効求人倍率は、2012年度の6.71倍から2022年度には2.04倍まで低下しています。
厚生労働省の推計では、今後10年程度は需要と供給が均衡するものの、2045年には最大で約10万人の薬剤師が過剰になると予測されています。ただし、これはあくまで全体の需給バランスであり、地域偏在による薬剤師不足は依然として課題とされています。
参照元:
厚生労働省/医師・歯科医師・薬剤師統計、e-Stat一般職業紹介状況(職業安定業務統計)「職業別労働市場関係指標(実数)(平成23年改定)(平成24年3月~)」、厚生労働省/薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会参考資料
これから求められる薬剤師の役割・スキル・知識

薬剤師として「必要だ」と思われる人材になるため、今後求められてくる役割やスキル・知識について5つご紹介します。
①専門的な知識・資格を身につける
対物業務が自動化される中で、薬剤師にはより高度な薬学的知見が求められます。
日々の業務に加え、専門的な知識を深めるための資格取得がキャリアアップの鍵となります。がん、感染症、妊婦・授乳婦、小児、精神科、栄養など、さまざまな領域で認定・専門薬剤師の資格が作られ、いずれの資格取得者も転職市場でニーズが高いです。
例えば、全ての薬剤師にとって必須ともいえる「研修認定薬剤師」は、かかりつけ薬剤師の要件の一つであり、自分の知識をアップデートし続ける姿勢の証明にもなります。
また、介護分野との連携に強みを発揮する「ケアマネジャー(介護支援専門員)」の資格を取得すれば、在宅医療や地域包括ケアシステムにおいて、ハブとして活躍できるでしょう。
これからの時代に有利な専門・認定薬剤師の資格とは?
特に需要が高まっているのが、専門性の高い領域に特化した認定資格です。
例えば、「がん薬物療法認定薬剤師」は、抗がん剤の高度な知識を活かして副作用モニタリングや支持療法を担います。
「在宅療養支援認定薬剤師」は、在宅医療の現場で患者やその家族に寄り添い、最適な薬物療法を支援します。
また、「緩和薬物療法認定薬剤師」は、終末期の患者の身体的・精神的苦痛を和らげるための専門家です。
【これからの時代に有利な専門・認定薬剤師の資格】
| 資格名 | 主な取得条件 | 活躍が期待できる職場 |
| がん薬物療法認定薬剤師 | 薬剤師実務経験3年以上、病院・診療所でのがん薬物療法の実務経験3年以上、実技研修・講習・試験など | がん診療連携拠点病院、がん専門病院 |
| 在宅療養支援認定薬剤師 | 薬剤師実務経験3年以上、薬局または病院・診療所での在宅業務経験など、講習・事例報告・試験など | 在宅療養支援をする薬局、病院 |
| 緩和薬物療法認定薬剤師 | 薬剤師実務経験3年以上、緩和ケア領域の実務経験1年以上、学会発表・講習・試験など | 緩和ケアチームのある病院、ホスピス |
資格取得は、特定の領域で質の高い薬物療法を提供するプロフェッショナルとしての価値を大きく高めることにつながります。
参照元:
日本病院薬剤師会|がん薬物療法認定薬剤師認定申請資格、日本在宅薬学会|在宅療養支援認定薬剤師、日本緩和医療薬学会|日本緩和医療薬学会緩和薬物療法認定薬剤師申請資格
資格取得のメリットと学習計画の立て方
専門・認定資格の取得は、キャリアの選択肢を広げ、年収アップに直接つながる可能性があります。
資格手当を支給する企業も多く、転職市場においても高度な専門性を持つ人材は高く評価されます。効率的に学習を進めるためには、計画性が重要です。
効率的な学習スケジュールの組み方と継続のコツは、以下のとおりです。
● 隙間時間を活用する
● 学習仲間を見つける
最終的な資格取得から逆算し、月単位・週単位の学習目標を具体的に立てます。
学習は、通勤時間や休憩時間などを活用して、アプリやオンライン教材で少しずつでも学習を進める習慣をつけましょう。同じ目標を持つ同僚やSNS上のコミュニティと情報交換することで、モチベーションを維持しやすくなります。
②コミュニケーション能力
対物業務から対人業務へと仕事内容の軸足が移る中、かつてなく高まっているのがコミュニケーション能力です。
さまざまな年齢層・病態の患者と接する薬剤師は、相手に合わせて適切なコミュニケーションをとっていく必要があります。ただ薬の情報を伝えるだけでなく、患者の話に耳を傾け、不安や悩みに共感する姿勢が求められます。
特に、リフィル処方箋の対応では、患者の表情や何気ない言葉から体調の変化や副作用の兆候を察知し、適切な受診勧奨につなげる観察力が必要です。 時には不安に寄り添い、時には誤解を解くために説明をおこなうなど、柔軟に対応することが重要です。
さらに、薬剤師は、医師や看護師、理学療法士、介護士など多くの職種と連携しながら仕事をしていかなければなりません。
お互いの知識や経験を尊重しつつ、必要な場面では薬剤師として意見を主張しなければなりません。医師や他の医療スタッフとの円滑な連携にもコミュニケーション能力は不可欠です。
③IT・DXスキルを習得し活用する能力
国が推進する医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れに乗り遅れないためにも、IT・DXスキルは必須です。
電子処方箋は、重複投薬や併用禁忌のチェックをより確実にする一方で、薬剤師にはシステムを適切に運用する能力が求められます。また、オンライン服薬指導では、画面越しの患者の状態を正確に把握し、適切な指導を行うためのスキルが必要です。
電子薬歴や各種の医療情報システムを使いこなし、データを薬学的知見と結びつけて患者のケアに活かす能力が、これからの薬剤師の価値を左右します。
④地域医療を支える「かかりつけ薬剤師」としての役割
高齢化が進む日本では、地域全体で患者を支える「地域包括ケアシステム」の構築が急務です。その中で中核的な役割を担うのが「かかりつけ薬剤師」です。
担当する患者の服薬情報を一元管理し、24時間体制での相談対応や在宅医療への積極的な関わりが求められます。
特に在宅医療では、医師や看護師、ケアマネジャーなど多職種と密に連携し、カンファレンスに参加して薬の専門家として意見を述べたり、服薬状況を共有したりするコミュニケーションが重要になります。
地域に根ざした健康の相談役として、住民から信頼される存在になることが不可欠です。
⑤予防医学やセルフメディケーションの知識
高齢化が進むにつれ、社会保障費の増大が問題となっています。薬剤師として、病気にならないための「予防」の知識を伝えたり、ちょっとした不調を自分で対処する「セルフメディケーション」をサポートしたりすることが求められてくるでしょう。
薬剤師は、地域の身近な医療従事者です。正しい知識を持ち、適切なアドバイスをすることで、予防医療に寄与できるでしょう。今後は、薬剤師がワクチン接種の担い手となる可能性もあり、公衆衛生の場での活躍が期待されます。
また、地域の薬局が開催する健康相談会やセミナーに積極的に開催し、住民の健康意識を高める活動が求められます。例えば、生活習慣病の予防に関するアドバイスや、禁煙サポート、セルフメディケーション税制の案内などを通じて、地域住民の健康を支えられます。
処方箋がなくても気軽に立ち寄り、健康に関する相談ができる場所として、薬局と薬剤師の価値を高めていくことが重要です。
\あなたに合った職場をお探しします!/
今後、より求められる薬剤師として働くためのポイント

時代の変化に対応し、患者や社会から必要とされる薬剤師であり続けるためには、継続的な努力が欠かせません。
重要なのは、常に患者の立場に立ち、目線に合わせて丁寧に接することです。専門用語を多用せず、分かりやすい言葉でコミュニケーションをとることを心がけましょう。
また、自分の成長だけでなく、後進や部下を指導することも、結果的に自分自身の学びを深め、組織全体の質を向上させることにつながります。薬剤師としてさらにステップアップするためのポイントを見ていきましょう。
①後進の指導・育成で自分も成長する
薬学生の実務実習で指導役を担う「認定実務実習指導薬剤師」になるなど、後進の育成に関わることは、自分の成長に大きく役立ちます。
指導薬剤師になるには、一定期間以上の実務経験や研修の受講が必要です。後輩や学生に教えるためには、自分の知識を再確認し、より深く理解する必要があるため、曖昧だった部分が明確になります。
また、指導を通じて新たな視点や疑問に触れることは、自分の思考を活性化させ、仕事を見直す良い機会にもなります。
②専門的な資格を取得する
専門薬剤師や認定薬剤師など、専門的な資格を積極的に取得しましょう。
特定の領域に対して専門的な知識があると対外的に示すことができるため、一般の方に対してもアピールとなります。自分の身近に専門的な知識を持つ薬剤師がいれば、安心して地域で療養することも可能です。
特に、「がん薬物療法認定薬剤師」や「在宅療養支援認定薬剤師」「緩和薬物療法認定薬剤師」などは、高齢化が進む日本でニーズが高くなる資格だと考えられます。求められる薬剤師になる第一歩として、資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
対人業務の専門性を高めるだけでなく、変化する医療環境に対応するための資格取得も有効です。
例えば、医療DXの推進に対応するため「医療情報技師」の資格を取得すれば、ITスキルの証明となり、院内システムエンジニアや医療情報システムの管理・運用といったキャリアパスも開けます。
また、多職種連携がますます重要になる中で、「ケアマネジャー(介護支援専門員)」の資格は、介護分野の知識を深め、医師や看護師、介護スタッフとの円滑なコミュニケーションを助ける強力な武器となるでしょう。
③語学を学ぶ
国際化が進む現代において、語学力は大きな強みとなります。
出入国在留管理庁の統計によると、2024年末の在留外国人数は過去最高の約349万人に達しており、医療現場で日本語を母語としない患者に対応する機会は確実に増えています。
英語はもちろん、中国語や韓国語といった近隣アジア諸国の言語を少しでも理解できれば、服薬指導をより正確にでき、患者に大きな安心感を与えることができるでしょう。
語学力は、他の薬剤師との差別化を図るための有効なスキルです。
参照元:出入国在留管理庁|令和6年末現在における在留外国人数について
④薬学的な思考力を磨き、処方提案につなげる
薬剤師は、医師とは違う視点から患者の病態や薬物療法を評価することが重要です。
情報を提示するだけならAIの方が正確におこなえるかもしれませんが、個々の患者に当てはめて評価をするという部分に関しては、まだ薬剤師の業務といえます。
情報を活用して評価するための知識や思考力を高めましょう。小児や高齢者など特殊な患者層の薬物動態を学んだり、CYPによる相互作用のリスクを評価する「PISCS」を実践したりすることで、個別化医療や安全性の向上に寄与できます。
これからの薬剤師は、処方箋通りの調剤だけでなく、薬学的知見に基づいた積極的な処方提案が求められます。
例えば、リフィル処方箋で来局した患者の症状が悪化していると判断した場合、ただ受診勧奨するだけでなく、考えられる副作用や効果不十分の可能性を医師に具体的に伝えることが重要です。
また、在宅医療の場面では、患者の嚥下機能に合わせて錠剤から散剤や液剤への剤形変更を提案するなど、生活の質を向上させるための介入が期待されます。
⑤在宅医療に関するスキルや知識を深める
高齢化に伴い、在宅医療のニーズはますます高まっています。在宅医療に関わる薬剤師には、薬の管理だけでなく、多職種と連携して患者の生活全体を支える視点が不可欠です。
特にターミナルケア(終末期医療)においては、医師や看護師と連携し、痛みをコントロールする麻薬の管理や、患者や家族の精神的な苦痛を和らげるためのコミュニケーションが重要な役割となります。
在宅医療の現場で頼られる存在になるために、関連スキルや知識を継続的に深めていくことが求められる状況です。
⑥在宅医療で必須となるフィジカルアセスメント能力
在宅医療では、医師の訪問頻度が限られるため、薬剤師が患者の体調変化を早期に発見する「目」となることが期待されます。そのために必須なのがフィジカルアセスメント能力です。
【在宅医療における薬剤師の観察ポイント】
| 観察ポイント | 内容 |
| バイタルサイン | 血圧、脈拍、体温、呼吸状態などを測定し、平常時との変化を観察する。 |
| 服薬状況 | 薬の飲み忘れや副作用の兆候だけでなく、薬を正しく管理できているか(アドヒアランス)を確認する。 |
| 生活環境 | 衛生状態や食事、家族のサポート体制など、患者を取り巻く環境にも目を配り、服薬に影響を与える要因がないか評価する。 |
観察で得た情報は、連絡ノートやお薬手帳、ICTツールなどを活用し、医師やケアマネジャーなど多職種と速やかに共有することが重要です。
⑦OTC医薬品やサプリメントの知識をつける
予防医学やセルフメディケーションを支えるため、OTC医薬品やサプリメントの知識をつけることも有用です。サプリメントや健康食品の種類は非常に多く、日本人の20〜30%程度の方が愛用していると報告されるなど、大きな市場となっています。
医療用医薬品との相互作用、腎機能や既往、生活習慣など、OTC医薬品やサプリメントを提案する上でも注意すべき点はたくさんあります。薬剤師としての知識や経験を活かせる分野と言えるでしょう。
「NR・サプリメントアドバイザー」という民間の資格もありますので、挑戦してみてはいかがでしょうか。
⑧変化の速い医療業界で学び続ける習慣づくり
日進月歩で進化する医療業界において、薬剤師として価値を提供し続けるためには、生涯にわたる学習が不可欠です。
最新の医療情報を得るためには、日本薬学会などの学会に積極的に参加したり、PubMedやJ-STAGEといった文献検索サイトを活用したり、製薬会社が提供するオンライン研修(e-ラーニング)を受講したりする方法があります。
モチベーションを維持するためには、以下のような工夫が有効です。
● 同僚と勉強会を開くなど、仲間と学び合う環境を作る
● 学習した内容を日々の業務でアウトプットする
学び続ける習慣こそが、変化の時代を生き抜く最大の武器となります。
薬剤師の転職なら、ヤクジョブ
転職の際には、ご自身の強みを的確にアピールする必要があります。とはいえ、自分では何が強みなのか、自覚できていない方も多いです。
理想的な転職を叶えるために、薬剤師の転職に特化した転職エージェントである「ヤクジョブ」を活用してはいかがでしょうか?職務経歴書の作成や面接の練習など、丁寧なサポートを受けられます。多くの求人から自分に合う職場を見つけたい方は、ぜひ「ヤクジョブ」にご相談ください。
よくある質問

薬剤師がなくなる理由は何ですか?
主な理由として、次の3点が挙げられます。
1, AIや自動化技術の進歩により対物業務が代替されつつあること
2,一般の方から仕事内容が見えにくく専門性が理解されづらいこと
3,患者に医薬分業のメリットが十分に伝わっていないこと
複合的に理由が絡み合い、「薬剤師は不要では?」という意見につながっています。
今後、薬剤師は需要がありますか?
はい、需要はあり続けますが、求められる役割が変化します。
高齢化社会の進展に伴う在宅医療のニーズ拡大や、国が推進する「かかりつけ薬剤師」制度、地域包括ケアシステムにおいて、薬の専門家としての薬剤師の役割はますます重要になります。
対人スキルや専門性を高めることで、将来性のあるキャリアを築くことが可能です。
\あなたに合った職場をお探しします!/
まとめ
「薬剤師はいらない」という声は、業務の自動化や仕事内容の変化を背景に生まれています。
しかし、それは薬剤師が不要になることを意味するわけではありません。むしろ、機械的な対物業務から、専門的な知識とコミュニケーションを活かした対人業務へと役割がシフトしているのです。
未来を見据えてスキルを磨き続ける薬剤師は、これからも地域医療に不可欠な存在として輝き続けるでしょう。