「社会人から薬剤師って目指せる?」と考えている方もいるのではないでしょうか。
社会人からでも薬剤師になれます。ただし、6年間の薬学教育と国家試験合格が必要なため、時間的・経済的な負担は大きく、相当な覚悟が必要です。
そこで、今回は、社会人から薬剤師になる方法や薬剤師として必要な能力、各職種で求められるスキルについて紹介します。転職をしようとする場合の、参考にしてください。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)社会人や主婦でも薬剤師を目指せる?

社会人や主婦からでも薬剤師になれます。ただし、6年間の薬学教育と国家試験合格が必要なため、時間的・経済的な負担は大きく、かなりの覚悟が必要です。
国公立大学であれば年間約60万円、私立大学であれば年間約200万円の学費が6年分かかります。さらに、授業や実習でアルバイト等も十分にはできないことから、在学中は大幅な収入減になるでしょう。
特に、仕事や家事との両立が必要な場合は、周囲のサポートと綿密な計画が不可欠になってきます。
また、卒業後も20代半ばの同級生と比較され、就職活動で厳しい目で見られる可能性も、ゼロではありません。
薬剤師資格を取得する条件
薬剤師になるためには、6年制大学の薬学部を卒業することが必須条件となります。
在学中は化学や生物学などの基礎科目に加え、薬理学、製剤学、医療薬学などの専門科目を履修し、長期に渡る病院や薬局での実務実習もしなければなりません。
卒業すると薬剤師国家試験の受験資格が得られますが、この試験に合格することで、晴れて薬剤師として働くことができます。なお、4年制の薬学部卒業では薬剤師になれませんので注意が必要です。
薬学部入学に必要な偏差値と学力レベル

薬学部の入試難易度は、大学によって全く異なります。場所にこだわらなければ、入学すること自体は難しくないとも言えます。
たとえば、国公立大学は全体的に偏差値が高く(偏差値57.5~67.5)、また、2025年現在のところ、編入学試験や社会人入試を実施していません。国語や社会を含む共通テストと、数学・英語・化学等の二次試験を突破する必要があります。
一方、私立大学の場合、入試の難易度はさまざま(偏差値35~60)で、自身に合った難易度の大学を選べば入学はできますが、国公立大学と比較して学費が高額です。私立大学では社会人入試や編入学試験を実施しているところも多いため、文系学部出身の方や、大学を卒業してから年数が経過している方などでも、挑戦しやすいかもしれません。
国公立大学薬学部の偏差値と入試難易度
国公立大学の薬学部の数や定員が少ないこと、学費が安いために倍率が高いことなどから、偏差値が高くなっていると考えられます。
| 偏差値 | ||
| 上位 | 東京大学 理科二類 | 67.5 |
| 京都大学 薬学部薬学科 | 65 | |
| 大阪大学 薬学部薬学科 | 62.5 | |
| 下位 | 東北大学 薬学部薬学科 | 60 |
| 岡山大学 薬学部薬学科 | 60 | |
| 広島大学 薬学部薬学科 | 57.5 |
私立大学薬学部の偏差値と選択肢の幅
私立大学の薬学部は非常に多く、薬学部全体に占める定員の割合も92%です。難易度や倍率も大学によりさまざまで、偏差値の低い薬学部では定員割れのところもあります。大学を選ばなければ、入学難易度は高くありません。
| 偏差値 | ||
| 上位 | 慶應義塾大学 薬学部薬学科 | 60 |
| 東京理科大学 薬学部薬学科 | 60 | |
| 星薬科大学 薬学部薬学科 | 55 | |
| 下位 | 帝京大学 薬学部薬学科 | 35 |
| 日本薬科大学 薬学部薬学科 | 35 | |
| 東北医科薬科大学 薬学部薬学科 | 35 |
社会人から薬剤師になる方法

社会人から薬剤師になるのはかなり難しいけれども、不可能ではありません。強い意志と資金があれば、社会人から薬剤師になれます。
社会人が薬剤師になるためには、次の3つのステップがあります。
● 薬学課程の修了
● 薬剤師国家試験への合格
以下で1つずつ詳しく説明します。
薬科大学・大学の薬学部への入学【偏差値・入試形式】
社会人が薬剤師になるには、まず薬科大学・大学の薬学部へ入学する必要があります。
私立大学の入学試験は比較的難易度が低め(偏差値35〜60)ですが、学費が高くなることが多いようです。国家試験の合格率が低い大学もあります。
一方、国公立大学は私立と比較すると学費は安いものの、入学試験のハードルが高く(偏差値57.5~67.5)なっています。入学試験の難易度と学費の両方を考えて、目指す大学を決めましょう。
全国に薬科大学や薬学部のある大学は、「日本薬剤師研修センター」のホームページで紹介されているので、以下からご確認ください。
参考:公益財団法人日本薬剤師研修センター「全国の薬科大学及び薬学部のある大学」
なお、多くの大学では別に社会人枠を設けて試験を実施して合否を判定します。また、既に大学を卒業している場合は編入学できる場合もあります。社会人枠の試験や編入学の場合、試験内容が異なり、面接や小論文などが中心です。
一部、化学や英語などの基礎学力の試験を課す大学もありますが、高校卒業レベルの内容ですので、理系大学を卒業している方はさほど難しいと感じないかもしれません。志望理由のプレゼンテーションがある大学もありますので、ご自身の得意分野やアピールポイントに合った試験が受けられる志望大学を選ぶと良いでしょう。
入学後の仕事との両立を考え検討するのをおすすめします。
6年間の薬学課程を修了する
薬学部での6年間は、基礎科目から専門科目まで幅広い学習が必要です。特に社会人学生は、仕事との両立や久しぶりの学習に戸惑うことも多いため、効率的な学習計画が重要です。
4年次までに基礎薬学を学び薬学共用試験(CBT、OSCE)を受験、5年次には病院・薬局での実務実習が約5か月間あります。薬学共用試験に合格しなければ、進級して実務実習に行くことができません。
合格率は約95%と高いですが、薬学共用試験に合格できず留年・退学する学生は一定数います。同級生と協力し合いながら、しっかり勉強することが大切です。
最終年度は、卒業研究と国家試験対策に重点を置いたプログラムをこなします。卒業試験に合格できずに留年する学生も少なくありません。計画的に、長期間にわたって幅広い科目の学習を継続する体力・精神力が求められます。
暗記科目も多いため、試験続きの学生生活は苦しいと感じることも多いかもしれません。ですが、社会人経験を活かした実践的な視点は、特に臨床系の科目や実務実習で強みになるので自信を持って学習に取り組んでください。
薬剤師国家試験への合格
薬剤師国家試験は年1回、2月に実施される試験です。試験範囲は6年間で学んだ全科目におよびます。2025年2月に実施された第110回薬剤師国家試験合格率は、68.43%でした。
【第110回薬剤師国家試験合格率】
| 合格率 | |
| 全体 | 68.85% |
| 新卒 | 84.96% |
| 既卒 | 43.94% |
| 国立大学 | 83.75% |
| 公立大学 | 82.88% |
| 私立大学 | 67.52% |
参考:「第110回薬剤師国家試験の結果について」(厚生労働省)
薬剤師国家試験に合格後、薬剤師免許申請を行い、名簿に登録されて免許証の交付を受けます。
社会人経験者の強みは実践的な理解力ですが、基礎科目の復習には特に注意が必要です。大学での定期的な模擬試験や補習を積極的に活用し、苦手分野を早期に克服することが合格への近道となります。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)社会人から薬剤師を目指す際の注意点

強い意志と十分な資金の他にも、必要なこと・知っておくべきことはいくつかあります。在学中は学業に専念しなければならないため、収入は大きく減る一方で、高額な学費が必要です。
また、就職活動の際には、若い同期と比較されることがあります。薬剤師として働く年数が少なくなるため、生涯年収もストレートに薬剤師になった人と比較すると少なくなるでしょう。社会人から薬剤師になるには、良い面だけでなく、ネガティブな側面も少なからずあるということです。
そして、社会人から薬剤師を目指す場合には、以下のようなことに注意する必要があります。
● 社会人編入ができる大学もある
● 薬学部の課程にかかる学費が高額である
● 社会人から薬剤師になるまでにかかる期間が長い
● 薬剤師を目指すための準備・勉強がハード
1つずつ詳しく説明します。
夜間大学や通信制大学はない
現在、薬学部では夜間課程や通信制の課程は設けられていません。これは実験・実習が多く、対面での授業が必須であるためです。
そのため、フルタイムで働きながら薬学部に通学することは極めて困難であり、退職や転職を含めた生活設計が必要となります。
社会人編入ができる大学もある
一部の薬科大学では社会人編入制度を設けています。編入学試験では、英語や化学など基礎学力に加え、面接などによる選考が行われます。また、大学によっては既修得単位の認定制度があり、以前の学歴に応じて一部科目が免除されることもあります。
ただし、編入学年は主に2~4年次までで、実施している大学も限られているため、事前に十分な情報収集が必要です。また、編入学試験を実施する時期は大学によって異なるため、受験のスケジュールも併せて確認しておくことをお勧めします。
編入学をおこなっている薬学部は、予備校などが一覧にして掲載している場合もありますので、参考になるでしょう。2025年8月現在では、北海道科学大学、北里大学などで編入学を実施しています。ただし、まとめられた内容を鵜呑みにせず、各自で大学のホームページから最新の情報を確認してください。
薬学部の課程にかかる学費が高額である
薬学部卒業までにかかる学費の目安は、以下のとおりです。
【薬学部の学費目安】
● 国公立大学:トータル350~450万円程度
● 私立大学:トータル1,000~1,200万円程度
| 入学料 | 年間授業料 | 6年間総額 | |
| 国立大学 | 282,000円 | 535,800円 | 3,496,800円 |
| 公立大学 | 〜282,000円※ | 535,800円 | 3,496,800円前後 |
| 私立大学 | 20〜50万円 | 110〜220万円 | 900〜1400万円 |
参考:全国の薬学部大学ガイド「大学 薬学部の学費について」
参考:文部科学省「公立大学基礎データ」
これは社会人が薬剤師を目指す上で大きな経済的ハードルとなっています。奨学金制度などの活用を検討する必要があるでしょう。
なお、この金額には入学金や施設設備費、実習費なども含まれています。また、通学費や教材費、生活費などの費用も考慮する必要があります。そのため、長期的な資金計画を立てることが重要です。
学費が高い理由
薬学部の学費が高額な主な理由は、6年制課程であることと、多くの実験・実習が必要なことです。特に実験設備や器具、試薬などの維持管理費用が大きく、また少人数制での実習指導も必要となるため、他学部と比較して運営コストが高くなっています。
さらに、5年次に行われる病院・薬局での実務実習にも多額の費用が必要となり、これも学費が高額となる要因の一つです。
社会人から薬剤師になるまでには6年以上かかるのが現実
薬学部での修学期間は最短で6年間ですが、実際にはそれ以上かかることがあります。
厚生労働省によれば、6年間で卒業できない学生は少なくなく、2012年に入学した学生のうち、国家試験に合格したのは6,651人であり、6年間で卒業して薬剤師国家試験に合格できるのは6 割に満たない状況でした。
留年したり卒業できなかったりする学生が多く見受けられますが、特に4年次での進級率が低いのは総合的な学力不足のようです。また、最終関門である薬剤師国家試験の合格率も例年65~75%程度で推移しており、卒業後も合格まで複数回の受験が必要なこともあります。
社会人学生の場合、基礎科目の理解に時間を要することが多く、7年以上の期間を必要とするケースも決して珍しくありません。そのため、長期的スパンでの生活設計と、十分な心構えが必要です。
入学前から卒業後までの資金計画や生活設計を、最低限の6年ではなく長めの期間で考えておくのが賢明です。特に仕事を辞めて学業に専念する場合は、より綿密な計画が必要です。
薬剤師は資格職のため、年齢は関係ないと考える方もいますが、必ずしもそうとは限りません。就職活動では「なぜ再受験をしたのか」「どうして薬剤師なのか」など細かな面に注目され、厳しい目で見られてしまうこともあります。また、スタートが遅い分、薬剤師としての生涯賃金は下がってしまうでしょう。
参考:厚生労働省「かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との 連携に関する調査研究」
参考:文部科学省「薬学部教育の質保証に係る調査に関する中間とりまとめ(案)」
薬剤師を目指すための準備・勉強はハード|入学前にすべきこと
薬学部での学習内容は、化学や生物学などの理系基礎科目から、薬理学、製剤学といった専門科目まで多岐にわたります。
特に社会人の場合、高校レベルの理系科目の復習から始める必要があることも多く、学習負担は相当なものとなるでしょう。また、4年次の共用試験(CBT・OSCE)や5年次の実務実習、卒業研究、そして最終的な国家試験と、重要な関門が複数あることにも注意が必要です。
そのため、入学前から基礎科目の復習を始めることをお勧めします。特に化学と生物学は薬学の基礎となるため、しっかりと準備しておくことが重要です。
数学や物理、英語の必修授業もあるため、高校卒業から時間が経過している方は、忘れている内容も多く、苦戦するかもしれません。入学前に復習しておくと良いでしょう。
薬学部入学前にすべき準備と対策

薬学部に合格したあと、実際に入学するまでにも準備が必要です。
たとえば、薬学部では、一定レベルの基礎知識があるという前提で授業が進みます。とくに、社会人入試などで基礎学力の試験なしに合格した方は、高校レベルの化学・生物・数学・英語などの復習をしておくことが大切です。前提がないままに授業を受けていても、内容についていけず、留年することになってしまうかもしれません。
事務手続きや、必要物品の準備も忘れずにおこないましょう。
入学料や授業料の納入、入学手続き書類の送付などは、期限が決められています。間に合わなければ入学の意思がないものとみなされてしまいますので、手続きはすぐにおこなってください。
必要な手続きや、購入物品などについては、大学から書類が送られてくるか、ホームページ上でダウンロードするようになっています。
学習面での準備|高校内容の復習が必要
薬学部では、化学・生物・物理・数学などの必修科目があります。高校卒業程度の知識はあるという前提のもとで授業が進められていきますので、高校卒業から時間が経っている方は、ある程度復習しておく必要があるでしょう。
とくに文系学部出身で薬学部へ入学する方などは、事前学習が必須です。薬学部では新しい化学反応や平衡について学習していきますので、高校化学の知識は全体的に必要になります。
薬学部の数学では、微分積分なども必要となるため、数学IIIの学習をしておくと良いでしょう。英語も、ライティング・リーディングなどに加え、プレゼンテーションの授業がある大学もあります。高校レベルの単語や文法は理解しておいた方が良いです。
大学によりますが、入学前課題として高校化学・生物・数学などのオンデマンド講義が用意されている場合もあります。
事務面での準備|入学手続きと必要な準備
試験に合格すると、入学前の準備内容について資料が送られてくることが多いです。手続き忘れのないよう、しっかりと確認しましょう。一般的には、以下のような準備が必要です。
大学で使用するソフトやシステムが確実に利用できるものを購入しましょう。大学生協などから案内があります。セットアップも済ませておくことが大切です。
● 実験用白衣
ほとんどの場合、大学で指定のものがありますので、推奨される枚数を購入しておきます。
● 教科書
大学ごとに指定される教科書は異なります。指定教材はしっかり準備しましょう。
薬剤師になるのに必要な能力・適性
薬剤師には、医療従事者として高い倫理観や強い責任感、日々進歩する医療についていくために勉強し続ける忍耐力などが求められます。それ以外にも、業務をしていく上で必要な能力や適性がありますので、知っておきましょう。
薬剤師の資格を持つ人材として、どの職種でも共通して求められるスキルについて3つお伝えします。
コミュニケーションスキル
薬剤師として働く上では、どんな職種であっても人とのコミュニケーションは必ずあります。基本的なコミュニケーションスキルは欠かせません。
相手に合わせて情報を正しく伝える能力、会話から相手のニーズを把握する能力、自分の考え(処方提案、疑義照会など)を伝え議論する能力など、社会人として必要なスキルは身につけておきましょう。
管理職の場合は、部下との信頼関係づくりや部署内の円滑な運営のためのコミュニケーションスキルも必要になります。自身の立場に合わせて、必要なスキルを1つ1つ身につけていくことが大切です。
薬や疾患に関する知識
医療機関だけでなく企業の場合でも、薬剤師は薬のスペシャリストとして採用されていることが多いです。
薬の知識は、あって当然のものとして扱われます。疾患に関する知識も、薬の知識とは切り離せないもの。総合的な知識を身につけなければなりません。
もちろん、医学・薬学の進歩に合わせ、新しい情報をキャッチし、アップデートしていく力も必要です。常に最新の情報を得るため、勉強会や学会に参加するなど、積極性・自主性があることもアピールポイントになるでしょう。
基本的なパソコンスキル
薬剤師資格の有無と直接的な関係はありませんが、社会人として、基本的なパソコンスキルは持っておく必要があります。薬歴の入力や在庫管理など、パソコンを使う作業は必ず発生するため、操作が苦手だと業務が滞ってしまいます。
どのような職場であっても、入力操作、簡単な資料作成の能力などは最低限身につけておきましょう。
その他持っていると役に立つスキル・能力
上記以外で、持っているとプラスアルファのアピールができるスキル・能力を3つご紹介します。
外国語スキル
外国語スキルは、最新の情報を入手するために論文やガイドラインを読むのに役立つだけでなく、患者とコミュニケーションをとる上でも非常に重要です。
コロナ禍では外国の方の来日が少なかったですが、最近は再び旅行客が増えてきています。特定の国の方が多く住んでいるという地域もあるでしょう。日本語を話せない患者は少なくありませんので、外国語を話せる薬剤師は重宝されます。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語など、地域のニーズにあった外国語の習得を目指してみてはいかがでしょうか?
経営スキル
経営のスキルは、調剤薬局やドラッグストアの店舗運営で役立ちそうだというのはイメージできると思います。それだけでなく、病院であっても、さまざまな加算や経営のことを意識した薬剤部運営は重要です。
将来的に管理職になりたい、スタッフや店舗(薬剤部)のオペレーションを担いたいという方は、経営のスキルを身につけると良いかもしれません。店舗運営に関わっていた方は、即戦力としてのアピール材料になります。実績を数値で示せると尚良いでしょう。
適応力
店舗異動や転職など、環境や業務内容が変わる機会はしばしば訪れます。
その度に適応に時間がかかって力を発揮できないようでは、能力を低く捉えられてしまい、もったいないです。
環境に慣れ、新しいルールを覚えて運用できる、新しい人間関係でも円滑なコミュニケーションが取れるといった能力は、チェーンの調剤薬局など異動の多い職場では重宝されます。
転職する場合でも、すぐに職場の環境や人間関係・ルール等に適応できる能力が高い人材は、即戦力として貢献度が高く、評価を得やすいです。ご自身がすぐに適応できるタイプなのかどうか、見極めておくと良いのではないでしょうか?
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)病院薬剤師に求められるスキル・能力

次に、「病院薬剤師」に特に求められるスキル・能力を解説します。
薬や疾患に関する知識
病院では、ほかの職種と比較して、求められる知識が幅広い傾向にあります。
勤務先の病院にはない診療科の治療にもある程度精通していなくては、入院患者に安心・安全な医療を提供できません。
内服薬だけでなく、注射薬や院内製剤などを扱っている点も特徴的です。
幅広く、専門的な知識が求められます。
コミュニケーションスキル
ほかの医療従事者とコミュニケーションを取り、薬剤師としての意見を伝え、必要に応じて議論するスキルが重要です。
病院では、さまざまな職種がチームとなって治療を進めています。薬剤師としての意見を強く押し出しすぎても、遠慮して何も言えなくても、良い治療を提供することはできません。医療従事者と円滑なコミュニケーションをとるスキルは、必須です。医師へ疑義照会する際も、簡潔にわかりやすく、かつ、根拠を示しながら話すという、薬剤師ならではの話し方が求められます。
また、入院する患者の中には、薬の服用ができておらず状態が悪化した方も少なくありません。
服用しなかった背景には、飲みにくさ、副作用への不安、生活スタイルに合っていないなど、さまざまな理由があり、理由に合わせた介入が必要です。患者と信頼関係を作りながら、服薬状況や治療への気持ちを聞き出し、治療がうまくいくよう導く必要があります。
患者の理解度もさまざまですから、一人ひとりに合わせた伝え方で服薬指導をすることも必要です。医療従事者・患者それぞれに合わせて柔軟なコミュニケーションがとれるスキルを身につけましょう。
認定薬剤師・専門薬剤師の資格
認定資格・専門薬剤師などプラスアルファの資格を持つ薬剤師は、ニーズが非常に高いです。「◯◯認定薬剤師を募集」というような求人もあり、給与交渉に繋げることもできます。
プラスアルファの資格があるというだけで、知識や経験があること以外にも、さまざまなことをアピール可能です。知識をアップデートし続ける積極性や、医療に貢献したいという意欲も伝わります。資格取得者を採用することで、その病院における医療の質向上・後輩の育成なども期待でき、病院にとってもメリットが大きいです。
たとえば、将来的に「がん薬物療法体制充実加算」の算定を目指しているという施設に転職を希望する場合、がん専門薬剤師の資格を取得していれば、即戦力として期待できるため、転職が叶いやすくなるでしょう。また、算定に関わるような資格であれば、給与交渉もおこなえるかもしれません。
薬局薬剤師に求められるスキル・能力

次に、「薬局薬剤師」に特に求められるスキル・能力を解説します。
薬や疾患、健康食品などに関する知識
薬局薬剤師は、相互作用や重複投与など、さまざまな医療機関からの処方薬を見逃しなくチェックしなければなりません。また、健康食品やサプリメントとの飲み合わせに関する相談もあるため、素早く調べて情報提供する機会もあります。
そういった状況にしっかり対応するために、薬だけでなく、疾患や健康食品などに関して、幅広い知識が必要です。
コミュニケーションスキル
入院患者さんを相手にするのとは異なり、薬局の中で、限られた時間の中で素早く状況を把握し、適切な指導をおこなうためのコミュニケーションスキルが必要不可欠です。患者さんの性格や理解度を会話の中で見極め、話し方・話す内容を瞬時に変えるなど、柔軟に対応しなければなりません。
コミュニケーションスキルに加え、ちょっとした会話から患者の体調変化やニーズなどを読み取るなど、観察力があると業務がよりスムーズに進められます。
もちろん、薬局スタッフと協力して業務をすすめていくためにも、コミュニケーションスキルは重要です。
たとえば、接客業や営業職の経験がある方は、お客様との関係性の作り方、会話の中で自然にニーズを探る方法、プレゼンテーション能力など、社会人経験があるからこその能力を持っています。薬剤師になってからも、患者や他の医療職とのコミュニケーションで活かすことができるでしょう。
認定薬剤師・専門薬剤師の資格
近年は、薬局薬剤師の方が取得できる資格もどんどん増えてきています。「外来がん治療専門薬剤師」「在宅療養支援認定薬剤師」などの資格はニーズが高く、持っていると役に立ちます。
認定薬剤師資格の取得は、かかりつけ薬剤師になるための要件でもあります。ぜひ、興味のある分野を見つけ、積極的に取得を目指していきましょう。
ドラッグストア薬剤師に求められるスキル・能力
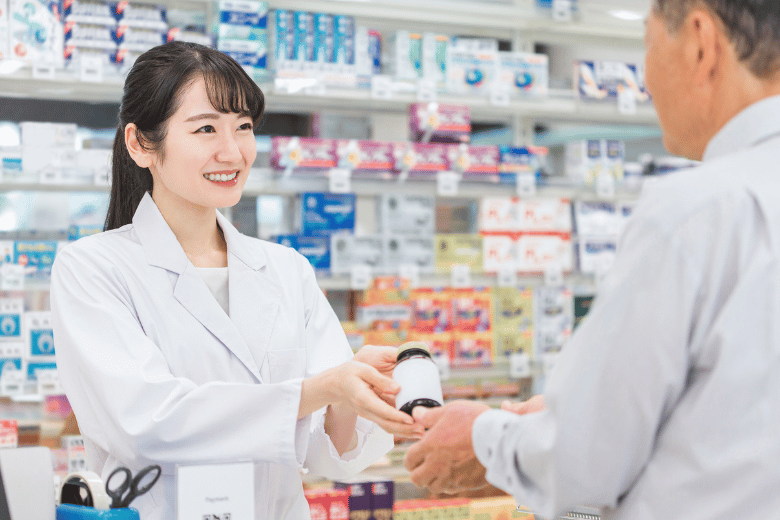
ドラッグストア薬剤師に求められるスキル・能力を解説します。
薬や疾患、健康食品などに関する知識
ドラッグストアの薬剤師は、薬局薬剤師と同様に、飲み合わせの確認が必要になる場合が多々あります。
そのため、市販薬だけでなく医療用医薬品、健康食品などに関する広範な知識が必要です。製品の情報を幅広く知っておかなければ、適切に提案することができず、次に述べる提案力にも関わります。
また、市販薬やサプリメント等を販売するにあたって、ただ飲み合わせを確認するのではなく、症状によっては医療機関の受診を促さなければなりません。疾患に関する知識も、常にアップデートしていく必要があります。
コミュニケーションスキル及び提案力
限られた時間や情報の中で相手のニーズを正確に把握し、症状や悩みに応じて適切な製品を提案する能力が求められます。
また、市販薬を提案する際には、ご家族構成・それぞれの持つ疾患なども踏まえて安全に使用できるようにすることが望ましく、状況を伺うにはコミュニケーションのスキルも欠かせません。
さらに、店舗の売上を意識しなければならないという点が、ドラッグストア薬剤師の独特な点です。
たとえば、サプリメントの購入に悩んでいる方にメリットをしっかり伝えて購買意欲を高める、プライベートブランドの市販薬でも効果は変わらないことを伝えて選んでもらうなど、提案力・営業力が試される場面で、社会人経験を活かすことができるのではないでしょうか。
健康やサプリメントに関する資格
「公認スポーツファーマシスト」や「NR・サプリメントアドバイザー」など、健康や健康食品に関する資格があると、相談を受けたときに自信を持って提案ができるでしょう。
スポーツファーマシストはまだ多くないですが、選手の人生がかかる問題ですから、ニーズは高いです。転職をお考えの方は、こういった資格を取得するのも良いかもしれません。
企業薬剤師に求められるスキル・能力

最後に、企業薬剤師に求められるスキル・能力を解説します。
企業の薬剤師は、医薬品や医療に関する知識が広く必要です。そして、その職種に応じてプラスアルファのスキル・能力が求められます。
たとえば、MRであれば医療従事者とのコミュニケーションスキル、提案力、プレゼン力が必須です。そのためには、関わる領域での深い専門知識も身につける必要があります。
CRC(治験コーディネーター)は、治験をスケジュール通りに進めるためのマネジメント能力が必須です。細かいところまでチェックするのが苦にならない性格の方に向いているといえるでしょう。
そのほか、管理薬剤師にはマネジメント能力、学術職には情報処理能力など、それぞれに特徴的なスキルが求められます。
職種によっては、情報を集めるために語学力も必要です。外資系企業では英語力が必須で、採用にあたって英語力の証明が課せられる場合もあります。
あなたに合った職場をお探しします
👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)よくある質問
薬剤師は独学でなれる?
薬剤師になるには薬学部を卒業し、国家試験に合格する必要があります。そのため、独学で薬剤師になるのは不可能です。必修の授業の多さ、実験・実習などの単位もあることから、通信制や夜間課程も存在しません。
35歳から薬剤師になれる?
薬剤師を目指すのに年齢制限はありませんので、何歳からでも目指すことは可能です。しかし、4年次の薬学共用試験(CBT、OSCE)や実習、そして国家試験と、勉強すべきことは多くあるため、努力が必要になります。
社会人入試と一般入試の違いは?
社会人入試では、学力よりは小論文や面接が重視される傾向にあります。基礎学力の試験を課す大学もありますが、一般入試とは内容が異なり、試験の内容だけで見れば比較的難易度が低いと言えるでしょう。社会人入試では、社会経験が薬剤師の業務にどのように活かせるかを伝えられること、また、薬剤師を目指そうと考えた動機や熱意などが評価されます。
まとめ
今回は、社会人から薬剤師になる方法や薬剤師として必要な能力、各職種で求められるスキルについて紹介しました。社会人からでも薬剤師になれます。
ただし、6年間の薬学教育と国家試験合格が必要なため、時間的・経済的な負担は大きく、大きな覚悟が必要です。また同じ「薬剤師資格保持者」であっても、職種によって求められることはさまざまです。ただ薬剤師資格があるというだけでは、ほかの求職者と差別化ができません。
薬剤師への転職をお考えの方は、それに向けて必要なスキルなどを身につけて準備をしておくと良いのではないでしょうか?薬剤師を目指そうと決心された方は、まずは、各大学の入試方法や試験内容について調べてみてください。ご自身の力で合格できる大学、魅力を感じる大学を選び、準備を始めましょう。
今から薬剤師になるのは難しそうだ…と断念してしまった方は、登録販売者の資格を目指してみてはいかがでしょうか。一般用医薬品の一部を販売できるようになる資格で、年に1回試験がおこなわれています。独学で目指すことも可能です。
ヤクジョブが運営するクラシスでは、薬剤師だけでなく、登録販売者の求人紹介もおこなっています。登録販売者として働きたい方は、ぜひご活用ください。

